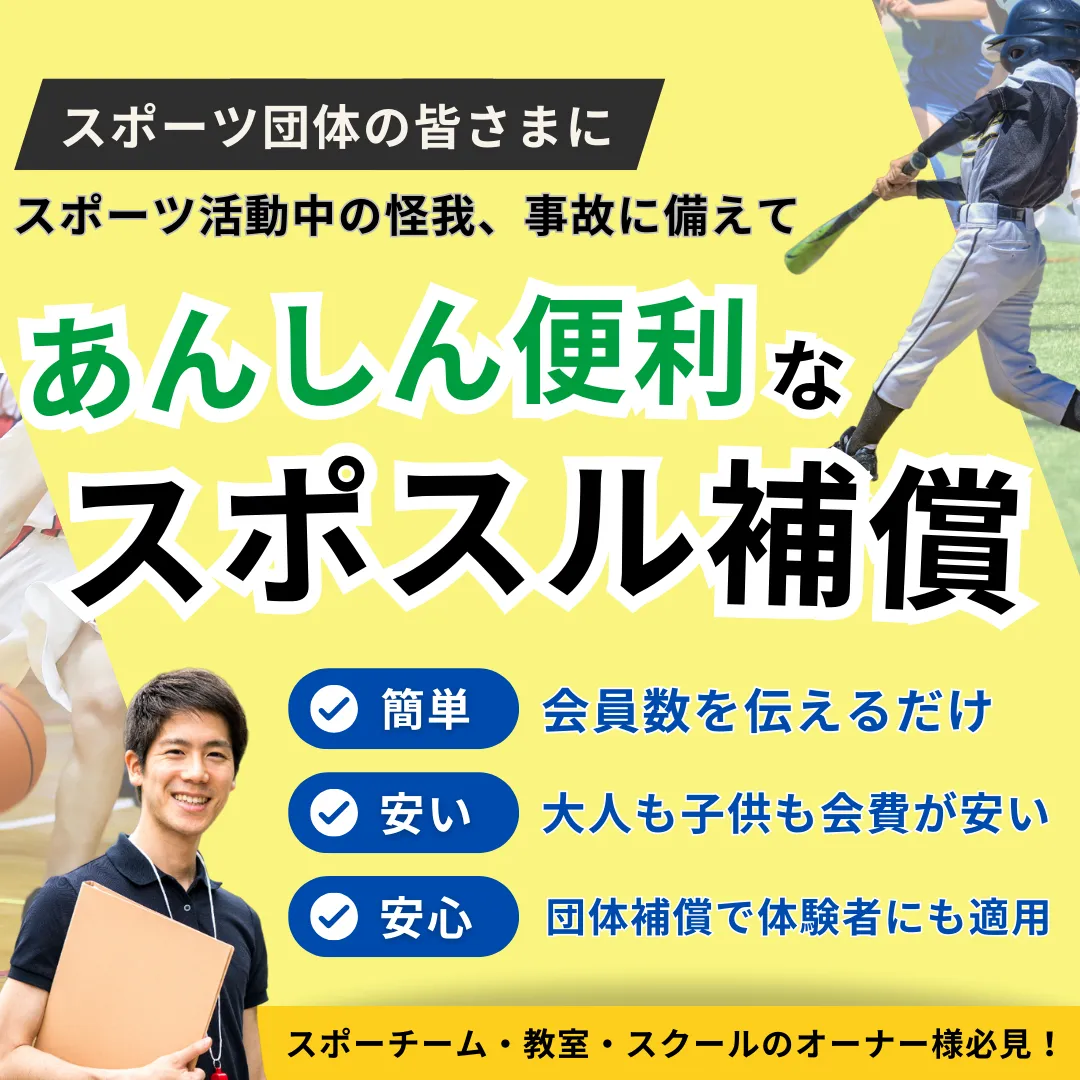将棋の頂上決戦の1つでもあるタイトル戦「名人戦」をご存知でしょうか。
そもそもタイトル戦とは、勝利することで、その称号を得ることができるというものです。
2021年でタイトル戦は「竜王戦」「名人戦」「王位戦」「王座戦」「棋王戦」「叡王戦」「王将戦」「棋聖戦」の8つ存在しています。
その中でも、竜王戦と名人戦は、将棋の頂上決戦とも言われています。
タイトル戦に勝利することで、プロ棋士であれば、誰もが憧れるタイトル保持者になることが出来ます。
今回は、その中でも将棋の「名人戦」について解説していきます。
将棋の名人戦について
名人戦は毎日新聞社、朝日新聞社、日本将棋連盟が主催している将棋のタイトル戦で、タイトル戦の中では一番長い歴史があります。
「〇〇名人」と呼ばれるようになるには、このタイトルで勝利する必要があります。
まずはその名人戦について解説して行きます。
名人戦の歴史
名人戦はタイトル戦の中で最も歴史があり、400年以上も前から続いているタイトル戦です。
江戸時代にタイトル戦が誕生した当初は、現行のような実力制ではなく、世襲制で「大橋本家」「大橋分家」「伊藤家」の3つの家の中で、最も強いものが「名人」と名乗っていました。
しかし、1934年に日本将棋連盟顧問の中島富治の発案から、東京日日新聞学芸部長の阿部眞之助が将棋の「実力名人戦」を企画し、現行の実力制名人戦が誕生することとなりました。
初代実力制名人は「木村義雄」がその位につくこととなります。
これが短期実力制名人位制度の誕生経緯です。
名人戦への挑戦権
将棋のプロ棋士はランク分けがされており、「A級」「B級1組」「B級2組」「C級1組」「C級2組」の5つのランクがあります。
棋士は1年を通してランク内で対局を行い、ランク内で成績が優秀だった棋士は1つ上のランクに昇格することが出来ます。
もちろん、成績が悪かった棋士は降格します。
そして、A級ランクの順位戦でその年1番成績が良かったプロ棋士が、その年の名人への挑戦権が獲得できるという仕組みです。
プロ棋士は名人戦にチャレンジするために、日々の対局で実力をつけていきます。
名人戦のルール
名人戦は7番勝負で行われており、先に4勝した方が勝利となります。
名人が勝てば、タイトル防衛で「名人」の称号を保持でき、挑戦者が勝てば、新しい「名人」の誕生です。
7番勝負は全国の料亭や旅館、あるいは文化施設など格式の高い場所で行われ、2008年以降、第1局を東京都文京区の椿山荘で行い、第2〜5局は公募より開催地が決定されます。
持ち時間は9時間で1局を2日かけて行い、この持ち時間はプロ棋士の対局の中で最長となります。
2日かけて戦うため、1日目の終わりには「封じ手」と呼ばれる作業を行います。
この封じ手とは、1日目の最後の1手を実際に指さず、紙に書いて封筒に入れ、記録係に渡す行為です。
これは、1日目と2日目の間に、次の一手を考える時間が生まれないようにするために行っています。
2日目の夕食休憩の時間があるのは、この名人戦だけです。休憩中に何を食べるのかメディアが注目したこともありました。
永世名人
名人には「永世名人」と呼ばれる方々がいます。永世名人とは、名人位を通算5期以上獲得した場合に与えられる称号です。
原則として引退後に、永世称号である「永世名人」を名乗ることが出来、永世名人を獲得した名人は「〇〇世名人」という称号となります。
最初の永世名人である木村義雄は、「十四世名人」と呼ばれ、「一」からスタートするわけではありません。
これは江戸時代から続く「終世名人制」は「十三世」が最後であり、それを引き継ぐためと言われています。
実力制名人制度になってからの「永世名人」は以下の通りです。
十四世名人:木村義雄
十五世名人:大山康晴
十六世名人:中原誠
十七世名人:谷川浩司
十八世名人:森内俊之
十九世名人:羽生善治
ただし、厳密には谷川棋士・森内棋士・羽生棋士は現役のために、まだ永世名人を襲位していません。
十四世名人の木村義雄先生は引退後に襲位しましたが、十五世名人の大山康晴先生、十六世名人の中原誠先生は現役中、様々な偉業を達成するなど、その成績から特例により現役で名乗ることを許されました。
歴代の名人達
歴代の名人たちはどのような方々がいるのでしょうか。
簡単に紹介していきます。
羽生善治
「将棋の名人といえば誰?」という質問をした時に多くの人が答える名前ではないでしょうか。
将棋のイメージを世間に広めた人といっても過言ではありません。
デビュー9年目という若さでタイトルを奪取しました。
加藤一二三
「ひふみん」という愛称で、メディアのバラエティー番組に登場することも多く、将棋のことはよく知らなくても加藤一二三先生のことは知っているという人も多いと思います。
バラエティー番組ではいじられることがあっても、将棋界ではトップ棋士の1人です。
森内俊之
森内俊之先生は2007年に十八世名人となりました。
受けが強い将棋をする棋風が特徴のため、その棋風は「鉄板流」とも呼ばれています。
谷川浩司
谷川浩司先生は当時、史上最年少の名人となり、その後、十七世名人の資格を得ることとなりました。
大山康晴
大山康晴先生は十五世名人・永世十段・永世王位・永世棋聖・永世王将の5つの永世称号を持っており、様々な偉業を成し遂げています。
名人戦ではタイトルを13連覇、通算18期という常人では考えられない大記録を持っています。
まとめ
今回は将棋の名人戦について解説しました。
名人戦のことを深く知ることで、TV放送している名人戦をより楽しく見ることが出来ます。
是非とも次回の名人戦を見てみてください。
【関連記事はこちら】⇩
・【将棋】ルールを解説!並べ方や駒の種類も知ろう!