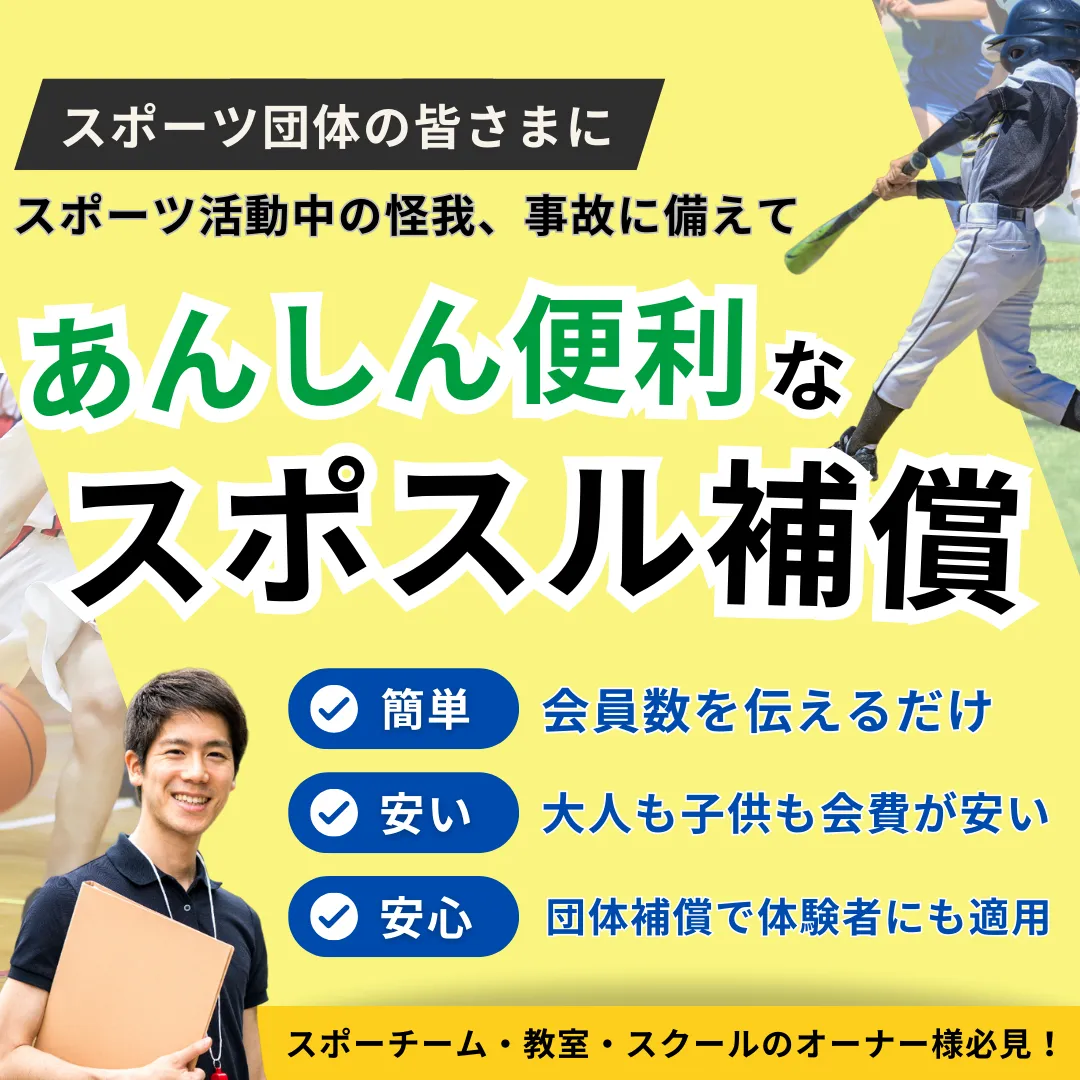小学生を中心に子どもから大人まで幅広い層に人気のドッジボール。全国に数多くのチームがあり、公式戦も盛んに行われています。
一方で関係者にとって悩みの種となっているのが「審判員の確保」。試合に必要な審判を集めることが難しく、常に人手不足が問題となっています。
ではドッジボールの審判とはどのような仕事なのでしょうか。ここでは子どもたちのためにもなるドッジボールの審判についてご紹介します。
ドッジボールには公式審判員が必要?
ドッジボールが日本に紹介されたのは明治42年。当時は円形のコートで行い、「円形デッドボール」と呼ばれていました。その後、大正6年に四角いコートの「方形デッドボール」が登場。大正15年にはドッジボールと改名されました。
それ以来、ドッジボールは身近なレジャーとして普及。各地の校庭や公園で行われる中で、様々なローカルルールが誕生することになりました。
そのような歴史を持つドッジボールを正式なスポーツにし、全国統一ルールで地域や国際交流を図る目的で平成3年に誕生したのがJDBA(日本ドッジボール協会)。
その後、日本体育協会、ワールドドッジボールアソシエーションへも加盟し、ドッジボールは正式なスポーツとなっていきました。
このような経緯があるため、練習試合やチーム内での試合には不要ですが、日本ドッジボール協会公式ルールで開催される公式試合には、JDBA公認審判員が必要になります。
JDBA公認審判員になるには?
JDBA公認審判員になるには公認審判資格取得認定会を受講する必要があります。
この取得認定会は満18歳以上なら誰でも参加可能。そのため選手の保護者が審判の資格を取ることもよくあります。
公認審判員の3つの級
JDBA公認審判員には3つの級があり、最初は誰でもC級からスタートします。そして種類によって審判ができる試合のグレードも上がっていきます。
・C級=都道府県大会まで
・B級=ブロック大会まで
・A級=全国大会を含む全ての大会
公認審判員の試験内容
公認審判資格取得認定会を主催する団体は、級によって異なります。
C級は都道府県協会が主催。認定会ではルールの説明や模擬体験試合実習、実技指導の後、マルバツ方式の筆記試験を行い、100点満点中の90点以上で合格となります。
B級はブロック競技部会が主催。C級公認審判員資格を取得してから満1年経過し、都道府県競技委員会から審判技術が優良だと推薦された人が受講できます。
こちらの認定会では、ルールの再確認や実習を行った後、筆記試験と実技試験を実施。実技では動作・試合の両方で試験を行い、筆記試験で90点以上、実技は共に80点以上で合格となります。
A級は日本協会競技委員会常任委員会が主催。B級公認審判員資格を取得してから満2年経過し、ブロック競技部会と日本競技委員会常任委員会から審判技術が優良だと推薦された人が受講できます。
試験内容はさらに高度に。論文、面接試験、実技試験が行われます。
ドッジボール審判の役割
ドッジボールの公式の試合では、主審1名、副審1名、線審4名の計6名が審判を行います。主審はイエローカードとレッドカードを持っていて、選手やコーチに警告や退場、失格を宣告することが可能。
また選手が試合中に抗議をすることは認められず、アウト、セーフ、ファールの判定やボールの支配権の決定は全て主審が行うことになります。
副審は主に主審の補佐をする役割。線審は主にワンタッチやノータッチの判定を行います。
難しい判定
どのようなスポーツにも微妙な判定はあるもの。ドッジボールにも審判を悩ませるプレイが存在します。それはアシストキャッチとイリーガルキャッチ。
遊びのドッジボールでは、誰かが弾いたボールを味方チームのメンバーがノーバウンドでキャッチすればセーフとなるのが一般的です。
しかし公式ルールでは、取りそこなって浮いた(ファンブルした)ボールをキャッチすればアシストキャッチとなりセーフですが、わざと弾いたボールをキャッチした場合はイリーガルキャッチというファールで、行った選手はアウトになるのです。
ファンブルかわざとかは審判の判断。難しい判定を下す必要があります。
また試合中にわざと相手の選手に触れると、タッチ・ザ・ボディーというファールになりますが、この判定も審判の主観。さらに選手はボールを持ってから5秒以内に投げるキープフォーファイブというルールがありますが、この5秒も主審の感覚次第ということになります。
他にも外野選手がボールに少しでも触れていれば、その後ボールがコート外に出てもボールの支配権を得られるワンタッチというルールがあるのですが、本当に触っているのかの判定が微妙な場合も。
線審はボールの飛ぶ角度や回転の変化で触れているかどうかをしっかり見極める必要があります。
まとめ
18歳以上なら誰でも挑戦できるドッジボールの審判。金銭的にはほとんどの場合謝礼などはなく、一般的にはボランティアで行うことになります。
一方で子どもたちの懸命のプレイをサポートできるのが審判の大きな魅力。
興味を持たれた方は、公認審判資格取得認定会を受講してみてはいかがでしょうか。
【関連記事はこちら】⇩
・【ドッジボール】公式審判になるには?役割や試験内容もご紹介!