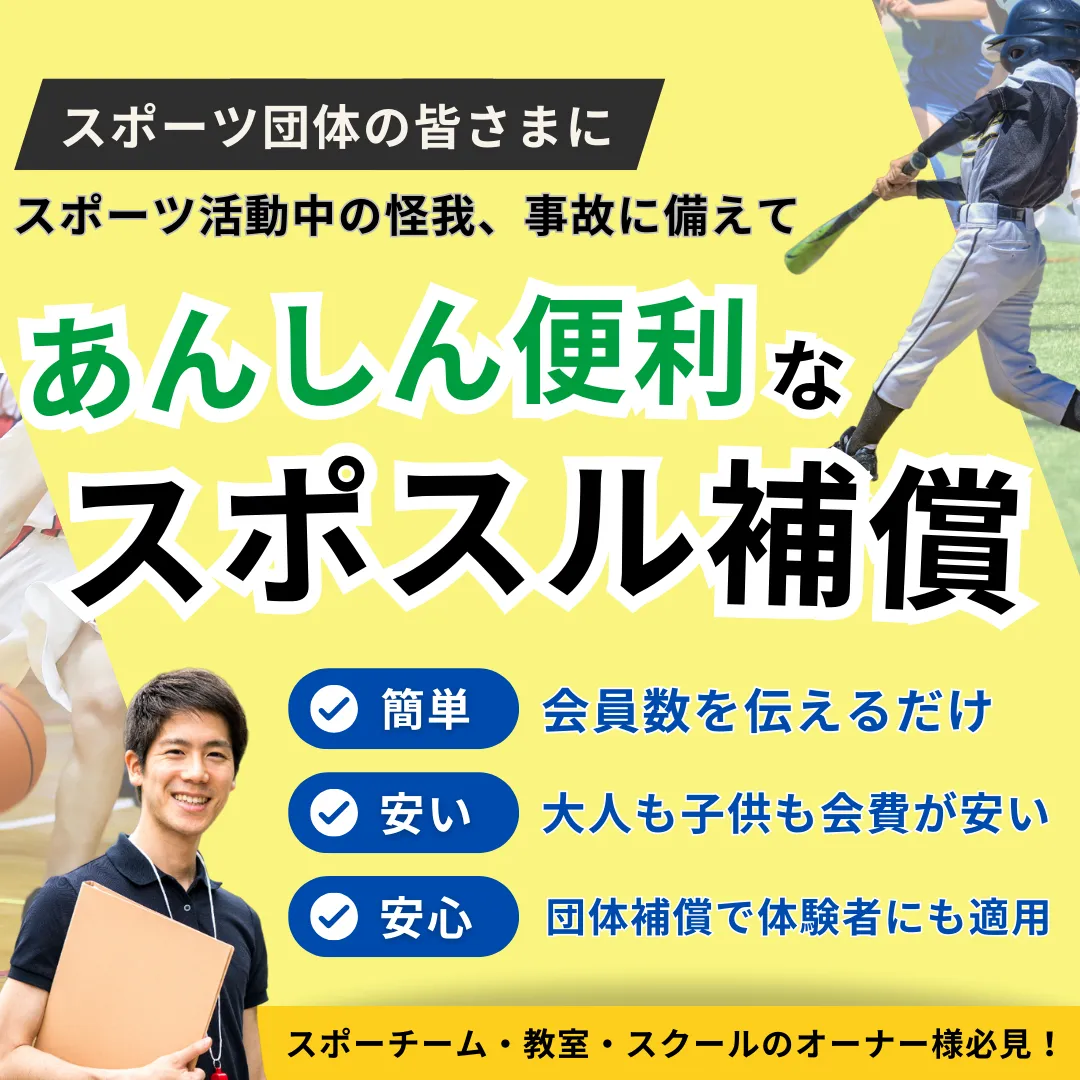バスケットボールでよくあるバイオレーションが、ダブルドリブルです。
定義はシンプルですが、該当するかどうかの判断が難しいのが、このダブルドリブル。
しっかり理解していないと、何度も繰り返してしまうことになります。
今回は、バスケットボールのダブルドリブルをご紹介。
どのようなバイオレーションなのか、詳しい定義とルールの詳細、注意点についてじっくり解説します。
【バスケ】ダブルドリブルとは
そもそもダブルドリブルとは、そしてバイオレーションとはどういう意味なのでしょうか。
定義
ダブルドリブルは、ドリブルを終えた後にもう一度ドリブルをしてしまうバイオレーションのこと。
バイオレーションとは、ファール以外の反則行為のことです。
審判の笛でゲームがストップ。相手ボールでの試合再開となってしまいます。
ダブルドリブルのジェスチャー
ダブルドリブルと判断したとき、審判はホイッスルを鳴らして、まず手を挙げます。
そしてドリブルをつくように交互に両手を上下するのがダブルドリブルのジェスチャー。
このジェスチャーでダブルドリブルがあったことをプレーヤーに伝えます。
【バスケ】ダブルドリブルについてのルール
ではダブルドリブルとは具体的にどのような反則なのか、ルールから詳細に分析していきましょう。
ドリブルの定義
まず問題になるのが、ドリブルの定義です。
ドリブルの定義は、日本バスケットボール協会(JBA)の「2023バスケットボール競技規則」24条-1-1に書かれています。
ドリブルとは、ライブのボールをコントロールしたプレーヤーが、ボールをフロアに投げたり叩いたり転がしたり、弾ませたりする動作である。
続いて24条-1-2には、こう書かれています。
ドリブルが始まるのは、コート上でライブのボールをコントロールしたプレーヤーが、ボールをフロアに投げたり叩いたり転がしたり、弾ませたりして、その後、他のプレーヤーが触れないうちに再びそのボールに触れたときである。
現実的にはボールを連続的に床に弾ませるプレーがドリブルですが、「他のプレーヤーが触れないうちに再びそのボールに触れたとき」が「ドリブルが始まるとき」であることが重要です。
ダブルドリブルの定義
ダブルドリブルを禁止しているルールは、日本バスケットボール協会(JBA)の「2023バスケットボール競技規則」の第24条−2です。
プレーヤーは、ひと続きのドリブルが終わった後、新たなドリブルをすることはできない。
一度ドリブルをやめた後、再びドリブルを始めるとダブルドリブルになります。
ここで問題になるのは「ドリブルが終わった」とはどういう状況をいうのかということ。
これが理解できないと、ダブルドリブルを繰り返すことになってしまいます。
ドリブル終了の定義
「ドリブルが終わった」ということに関して、競技規則の24条1−2には以下のように定義されています。
ドリブルが終わるのは、ドリブラーの両手が同時にボールに触れるか、片手または両手で同時にボールを支え持ったときである。
分かりやすいダブルドリブル
一般的に最も分かりやすいのは、ドリブルの後に両手でボールを持ってパスやシュートの体勢に入ったとき。
このときに相手ディフェンスにパスやシュートのコースを遮られているので、仕方なくもう一度ドリブルで抜こうとしたら、明白なダブルドリブルになります。
両手でドリブルをしたとき
明らかにボールを保持したとき以外でダブルドリブルを取られるのは、ドリブル中にうっかり両手でボールに触れてしまったとき。
「ドリブラーの両手が同時にボールに触れる」ことでドリブル終了となり、「ボールをフロアに投げたり叩いたり転がしたり、弾ませたりして、その後、他のプレーヤーが触れないうちに再びそのボールに触れた」ことで再びドリブルを行ったダブルドリブルだと判断されてしまいます。
ボールを掴むようなドリブル
ボールを掴むように長く手に持つドリブルをする人がいます。
これは審判によっては「ボールを支え持った」ということでドリブル終了と判断されます。
そのため、長く持ちながらドリブルを行うとダブルドリブルになりがちです。
ボールを下から支えるドリブル
ドリブルの癖で手を回すように使い、下から支えているように見える人もいます。これも「ボールを支え持った」ことでドリブル終了と判断されるダブルドリブルになりがち。
「ドリブルをやめてから再開したわけじゃないのに」と思っている人は、支え持ったように見える癖に注意が必要です。
【関連記事はこちら】⇩
・【バスケットボール】ルールについて徹底解説!初心者は反則に注意!
・バスケットボールの歴史・競技人口・ルール・大会【スポーツ辞典】
【バスケ】ダブルドリブルの疑問
ダブルドリブルについては、「このような場合はどうなるの?」という状況がいくつかあります。
それぞれの場面を解説しましょう。
ファンブル
判断に迷いがちなのが、ボールをファンブルしてからドリブルを行ったとき。
ファンブルとはボールが手につかずコントロールできない状態のことです。
競技規則の24条-1-4には、「以下の行為はドリブルではない」としてこう書かれています。
ドリブルを始めるときや終わるときにボールをファンブルすること。
このため、ファンブル後のドリブルはダブルドリブルとはならないのです。
ただし審判がファンブルではなく「ドリブルのミス」と判断した場合は、ダブルドリブルを取られる可能性もあります。
パワードリブル
両手でドリブルをするとダブルドリブルになってしまいますが、パスを受けたりリバウンドで競り勝ったりした後、最初に両手でボールをつくのはダブルドリブルとはなりません。
両手で力強くドリブルをついて、ディフェンスを中に力で押し込むテクニックはパワードリブルと言います。
ドリブルの途中でパワードリブルを挟むとダブルドリブルになりますが、最初のひとつきでパワードリブルを行うのはダブルドリブルとはならないのです。
リバウンド
リバウンドは、バックボードやリングに当たって跳ね返ってきたボールを取ること。
ドリブル後にシュートを放ち、そのリバウンドを自分で取ってドリブルをしたら、ダブルドリブルになるのでしょうか。
これはダブルドリブルにはなりません。
なぜかというと、ボールがゴールに当たった瞬間にドリブルはリセットされるから。
また競技規則の24条-1-4には、「以下の行為はドリブルではない」としてこのようにも書かれています。
バックボードを狙ってボールを投げ、再びボールをコントロールすること。
これはNBAなどでよく見られるプレー。バックボードにボールを当てて自らリバウンドを取り、シュートを狙います。以前はバックボードにボールを当てる行為もドリブルとされていたのですが、2019年にルールが変更。バックボードに当ててドリブルを再開するプレーはダブルドリブルではなくなりました。
まとめ
意外と取られることが多いダブルドリブル。
うっかりというよりはルールをよく理解していないために取られることが多いバイオレーションの一つです。
ドリブルとは何か、ドリブルを終えるとはどういうことかを理解すれば、ダブルドリブルを減らせるはず。
一方で相手に完璧にパスコースを塞がれ、確実にカウンターを受けそうな場面では、わざとダブルドリブルをして時間を稼ぐというテクニックもあります。
奥深いダブルドリブル。
しっかりと理解し、無駄なバイオレーションを減らしつつ、上手に活用してください。
【関連記事はこちら】⇩
・【バスケットボール】ドリブルのコツは〇〇!これで差をつけよう!
・【バスケットボール】コートサイズを調査!一般とミニバスを比較!