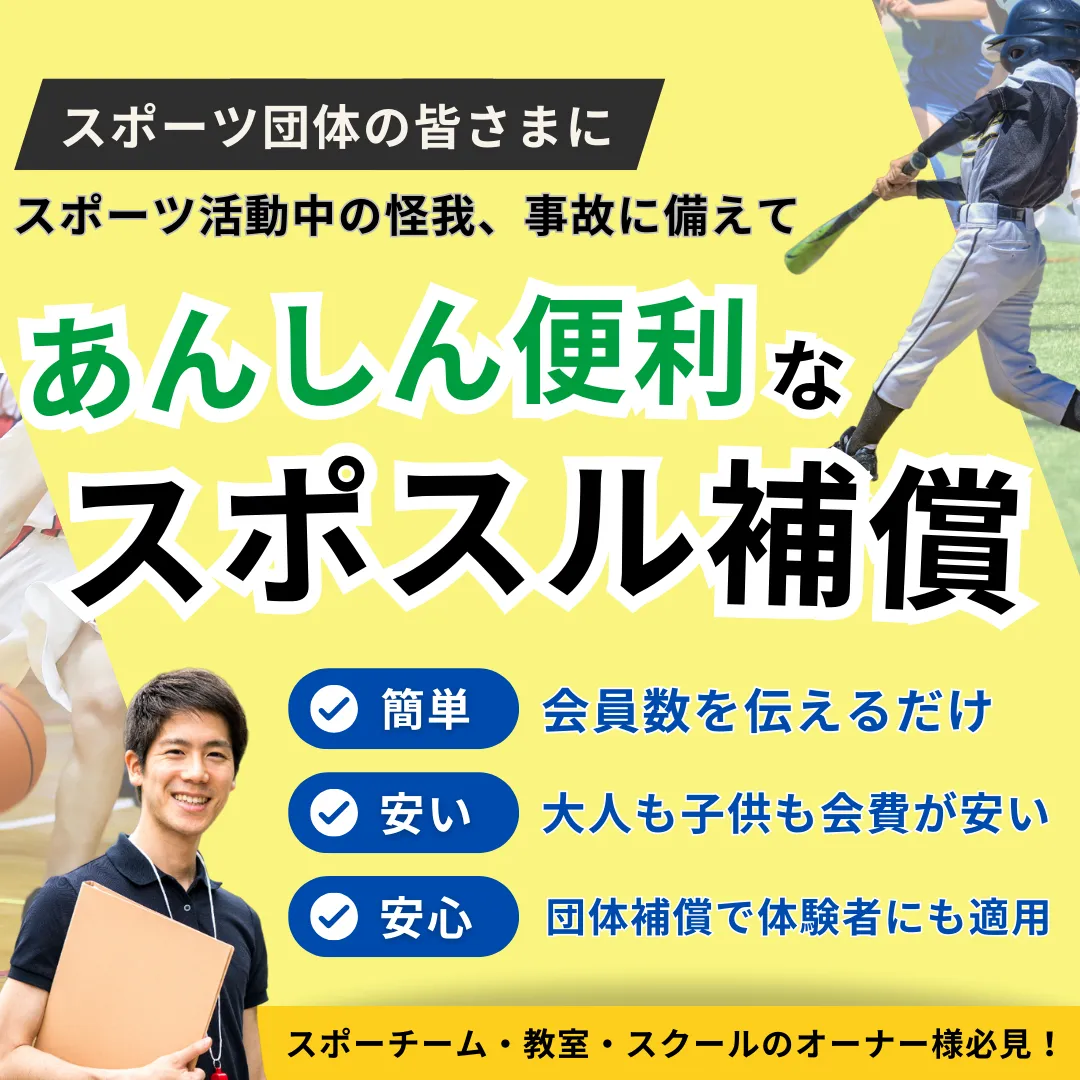スポーツといえば、身体を動かす競技を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。
確かに、スポーツ選手と聞いて、野球選手・バスケットボール選手・バレーボール選手・サッカー選手など、身体を動かすスポーツをイメージしがちです。
しかし、スポーツ基本法では、スポーツは身体を動かすことだけでなく、その他の身体活動も含まれます。
その他の身体活動、つまり、頭脳という身体の部位を使うものもスポーツということです。
そういったスポーツのことを、身体を動かす「フィジカルスポーツ」と分けて、頭脳を使う「マインドスポーツ」と呼んでいます。
マインドスポーツは様々ありますが、日本でよく知られたマインドスポーツである「囲碁」についてよくご存知でしょうか。
名前は知っているが、やったことがない、もしくはルールさえ知らないといった人が多いと思います。
今回はマインドスポーツの1つである「囲碁」について解説していきます。
囲碁について
囲碁と聞いて、その存在を全く知らない人はいないと思います。
しかし、詳しく内容を知っているという人は多くないでしょう。
昔は囲碁をやる人が多かったのですが、今や囲碁は日常生活であまり目に触れることが少なくなりました。
ただ、そんな囲碁も詳しく知っていけば、かなり奥が深く面白いゲームですが、現代のような囲碁になったのはどういった経緯があるのでしょうか。
まずは囲碁の歴史について解説していきます。
囲碁の歴史
囲碁の始まりは、4,000年くらい前の中国だと言われています。
中国で囲碁は対戦だけでなく、占いなどにも用いられたと言われています。
戦国時代では、囲碁を勉強することで政治や戦法を学ぶことが出来たため、武将や王も囲碁を楽しんでいました。
そこから、奈良時代に遣唐使が唐から持ち帰ったことで日本に広まり、平安時代には公家階級や僧侶たち貴族社会でも囲碁が楽しまれるようになります。
そして豊臣秀吉が天下を取った後、囲碁の強い人たちを全国から集め、そこで優勝した「本因坊算砂」が毎年給与を支払われるようになり、これが日本で最初の公認プロ棋士となりました。
江戸時代になると、幕府により囲碁は国技となり囲碁界の黄金期を迎えましたが、そこから江戸幕府の崩壊と共に、囲碁界は低迷期になりました。
しかし、1924年に日本棋院が創立され、1945年に戦争が終わり昭和30年以降になると、新聞やテレビなどメディアで囲碁が取り上げられるようになります。
そこから全国で囲碁が広まり、トップ棋士など、たくさんの棋士が生まれてきました。
囲碁のルール
囲碁のルールは簡単ですが、簡単だけでなく、そこに奥深さがあるところが好まれている理由です。
その基本的なルールを解説していきます。
黒と白が交互に打つ
碁盤はマスが描かれており、黒や白の碁石はそのマスが交差しているところに置きます。
一度置いた碁石は、将棋のように動かすことはできません。
先攻・後攻を決めるやり方は様々ありますが、プロ棋士も行っている「ニギリ」という決め方があります。
それは、白の碁石を持っているプレーヤーが、片手に好きな数だけ碁石を握り、握ったまま碁盤の上に手を置きます。
黒の碁石のプレーヤーは1個か2個どちらかを碁盤の上に置きます。
これは、白のプレーヤーが握っている碁石が奇数だと予想すれば1個、偶数だと予想すれば2個ということで、予想が当たっていれば黒のプレーヤーが先攻、外れていれば白のプレーヤーが先攻となります。
相手よりも陣地を多く囲った方が勝ち
陣地の大きさは、縦線と横線の交点の数のことです。
囲った陣地はマス目の外側は囲わなくても陣地の外側として扱い、最後に整地をして陣地が多くなった方が勝ちになります。
石は周りを囲むと取れる
相手の碁石縦横4ヶ所を囲むと、相手の碁石を取ることが出来ます。
取った碁石は最後整地をした際に、相手の陣地に置いて陣地を減らす役割があり、相手の碁石が2つ以上連なっている場合も全ての縦横の交点を囲むことで、相手の碁石を取ることが出来ます。
つまり、何個碁石が連なっていても、斜め以外の縦横の交点を全て囲むことで取ることが出来るのです。
碁石を置けない場所もある
交点であれば碁石を置くことが出来ると先述しましたが、実は置けない場所もあります。
それは、相手に囲まれている場所へは打つことが出来ないというルールですが、相手に囲まれている場所であっても、次に石を取ることが出来る場所には打つことが出来ます。
コウのルール
囲碁には「コウ」というルールがあります。
囲碁には、相手の碁石と自分の碁石が無限に取り合うことが出来る形になる場合があります。
その場合、最初に碁石を取られた方は、次にその碁石を取ることが出来ないというルールです。
こちらはイメージしにくいルールであるため、実際に碁盤に碁石を置いて理解した方が良いルールです。
色々な「コウ」の形があるため、その形を覚えてみてもいいかもしれません。
まとめ
今回は囲碁の歴史と、基本的なルールについて解説しました。
囲碁はとても簡単なルールですが、いざやってみると奥が深くのめり込んでしまいます。
頭脳戦のスポーツと言われるだけあって、次の1手だけでなく、数10手、数100手先を読み合いながら打っていきます。
プロ棋士であれば、常人では考えられないほど先の手を読んでいます。
必ずそこまで考えてやるという必要はありませんが、いざやってみると、その読み合いの虜になってしまうかもしれません。
【関連記事はこちら】⇩
・【囲碁】囲碁のプロ棋士までの道のり!その段位とともに紹介!