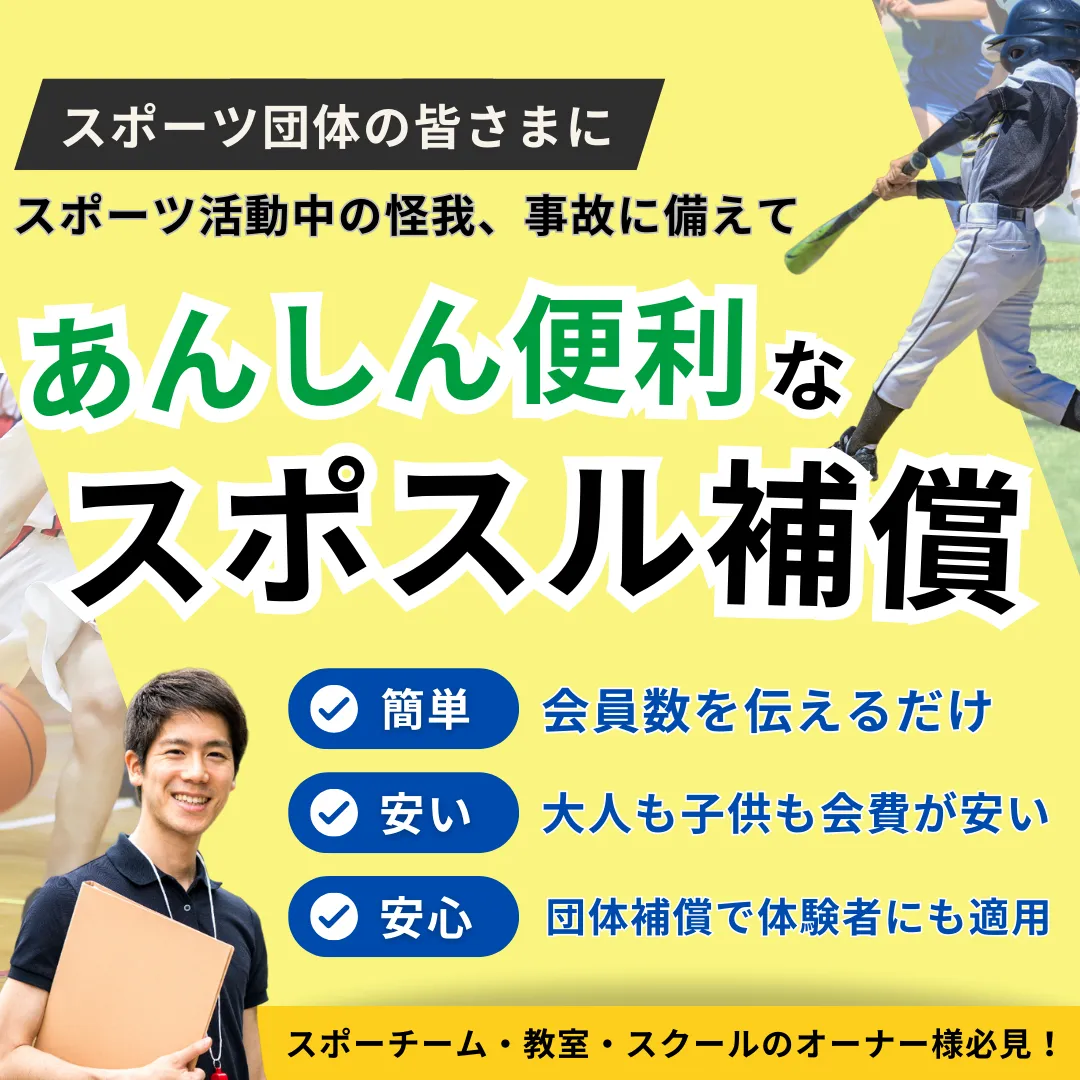近年の高校野球の延長戦はタイブレーク方式で行われます。
しかしこのタイブレーク、ルールがよく分からないという方も多いのではないでしょうか。
今回は、高校野球を中心に、野球のタイブレークをご紹介。
ルールや導入された経緯について解説します。
【高校野球】タイブレーク方式の意味
まずはタイブレークという言葉について解説します。
タイブレークといえばテニスが有名。テニスではゲームカウントが並んで長引いてしまう試合の決着を早くつけるために7点先取のゲームを行うのがタイブレークです。
そして野球やソフトボールのタイブレークも、同じように同点が続いてしまう試合の決着を早くつけるために行います。
通常の延長回との最も大きな違いは、最初から塁上にランナーを置くこと。
これによって得点が入りやすくします。
【関連記事はこちら】⇩
・【高校野球】球数制限は何球まで?経緯や規定詳細を調査!
・【高校野球】歴代優勝校一覧|優勝回数ランキングと特徴もご紹介!
ソフトボールのタイブレーク
実はタイブレークはソフトボールでは以前からかなり一般的です。
ソフトボールは投手戦になることが多く、延々と0点が続くこともあるため、これを解消するためにタイブレークが生まれました。
ISF(国際ソフトボール連盟)がこのルールを採用したのは1987年。
当初は延長10回から採用されていましたが、2002年以降は延長に入ってすぐの8回から行われています。
では野球ではどのようなルールで行われるのでしょうか。
開始イニング
ソフトボールではタイブレークは延長戦の最初から行われますが、野球ではルールによってさまざま。
10回から行う大会もあれば、数回は通常の延長戦を行ってからタイブレークに入ることもあります。
ランナー
タイブレークの最重要ポイントであるランナー。どのような状態からスタートするのかというと、満塁から行われる場合もあれば、ランナー1・2塁から始める場合もあります。
こちらも大会によって異なるのです。
塁に出る選手は、1塁ランナーの場合、その回の先頭打者の前の打順の選手。
2塁ランナーはさらに1つ前の打者で、3塁ランナーは2塁ランナーの前の打者が入ります。
アウトカウント
もうひとつ重要なのがアウトカウント。
タイブレーク制では、ノーアウト、または1アウトから始まり、これも大会によって異なります。
打順
もう一つややこしいのが、打順です。
通常は前の回の最後にアウトになった打者の次の打者から始まりますが、タイブレークには、この継続打順制の他に選択打順制というものもあります。
選択打順制は、前の回までの打順に関係なく、最初の攻撃をどの打者からでも開始できるというルール。
これも大会によってどちらを採用するかが異なります。
【高校野球】タイブレーク方式の具体的なルール
タイブレークのルールは、細かいところではかなり柔軟。
詳細は大会やリーグごとに決められます。
では高校野球のルールはどのようになっているのでしょうか。
開始イニング
開始イニングはこれまでは延長13回からでしたが、2023年春の大会以降は延長10回からとなりました。
つまりソフトボールと同じように延長の初回からタイブレークとなります。
試合終了と投球イニング数
タイブレークを行う代わりに、以前にはあった「延長は15回まで」というルールはなくなっています。
つまり決着がつくまで試合は続くことに。
ただし1人の投手が1日に投げられるのは15イニングまでとなっています。
ランナーとアウトカウント
タイブレークのランナーは1・2塁で、アウトカウントはノーアウトからとなります。
これによってかなり得点が入りやすくなるのです。
打順
打順は継続打順制。
通常通りに、前の回の最後にアウトになった打者の次の打順の選手が打席に入ります。
個人記録
タイブレークに入ると自動的にランナーが出ますが、ここで気になるのが個人記録。
例えば投手の自責点ついては「出塁した2人の走者は、投手の自責点としない」と決まっています。
そしてノーヒットノーラン(無安打無失点試合)は認められるのですが、残念ながらパーフェクト(完全試合)は認められないことに。
一方、打者の場合、自動出塁している2人の走者をからめた打点は認められます。
【高校野球】タイブレーク方式導入の経緯
現在のように高校野球にタイブレーク方式が導入されるまで、延長戦はどのように行われていたのでしょうか。
延長戦短縮の歴史
高校野球の全国大会が始まった1915(大正4)年から長い間、延長戦は勝負がつくまで無制限で行われていました。
しかし1958(昭和33)年の春季四国大会で徳島商の板東英二投手が準決勝で16回、翌日の決勝で25回を一人で投げきり、あまりにも過酷だと問題に。そこで1958年の夏から延長戦は18回までとされました。
続いて延長戦が短縮されたのは、42年後。
1998(平成10)年夏の大会で横浜高校の松坂大輔投手がPL学園を相手に17回250球を投げきったことがきっかけで、2000(平成12)年の春の大会から延長戦は15回に短縮されました。
タイブレークの登場
さらに試合時間を短縮し、投手の負担を減らすためにタイブレーク方式が導入されたのは2018(平成30)年。
まずは決勝戦以外の試合でタイブレーク方式を採用しました。
一方で決勝戦はそれまで通り最長15回まで延長戦を行うことに。ただし延長15回で引き分けの場合は再試合を行い、その試合はタイブレーク方式というルールでした。
そして2021(令和3)年の春の大会からは、決勝戦を含む全ての試合がタイブレーク方式となりました。
開始イニングの前倒し
高校野球のタイブレーク開始イニングは2022年夏の大会までは延長13回からでした。つまり延長10回から12回までは通常通りに行い、13回からはタイブレークということ。
しかし前述のように2023年の春の大会からはルールが変更され、延長10回からとなりました。
これは従来のルールでは現実的には12回までに決着がつくことが多く、しかもその間に投手には大きな負担がかかっていたため。
近年の酷暑への対策も兼ねてタイブレーク開始が早められたのです。
まとめ
高校野球に導入されているノーアウト1・2塁からというのは、ワールドベースボールクラシック(WBC)でも行われているタイブレークの国際基準。
ちなみに大学野球では2017年まで「選択打順制、1アウト満塁から」というルールでしたが、その後は国際基準に合わせて変更されています。
試合時間を短縮し、選手の安全を守るために導入されたタイブレーク。
10回からのスタートになったことでまた新たなドラマが生まれるのではないでしょうか。
【関連記事はこちら】⇩
・【高校野球】グローブ規定について|色・紐・刺繍の制限について!
・【コールドゲーム】点差や条件とは?高校野球以外も徹底調査!