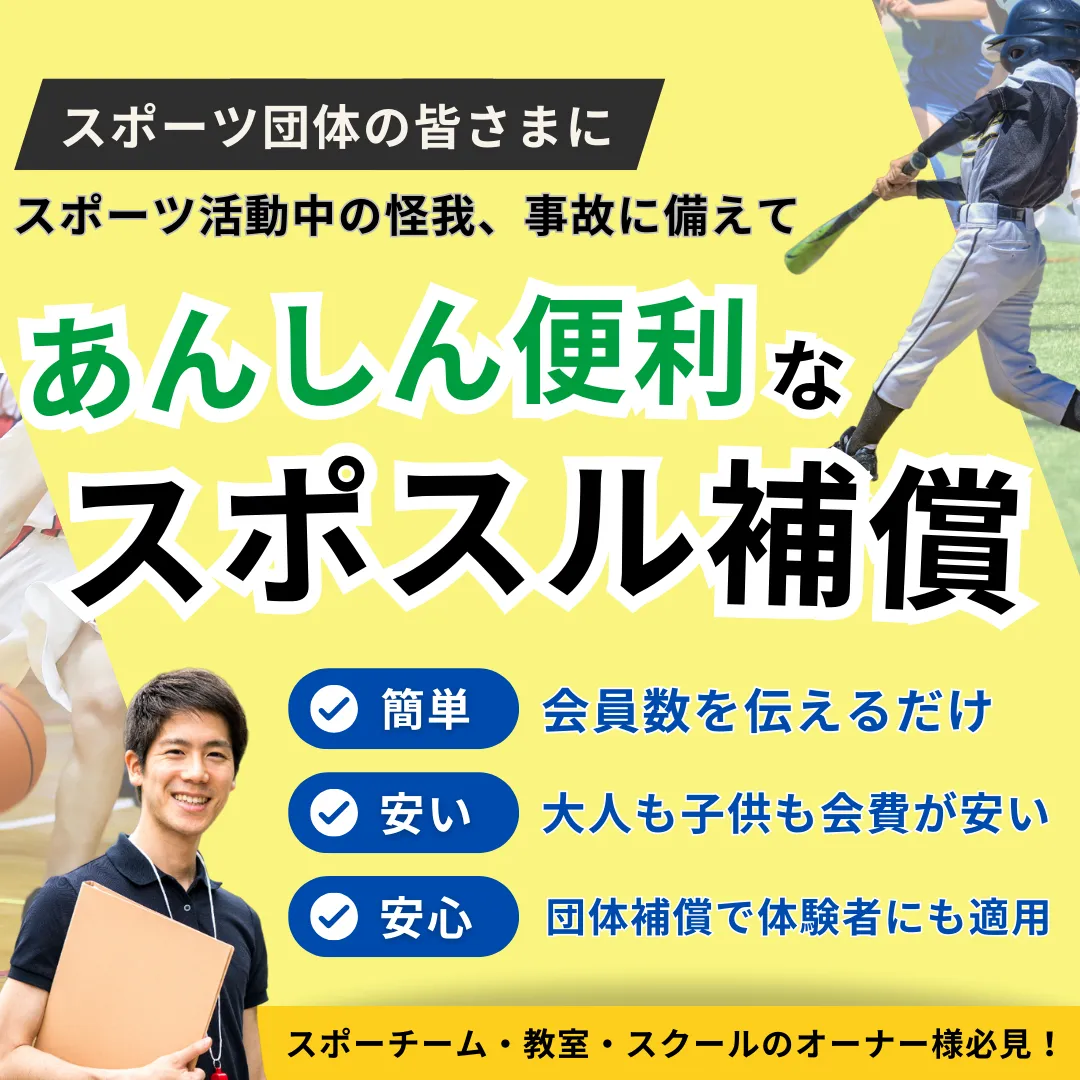お手玉は、日本伝統の遊び。
室町時代に中国から伝わり、聖徳太子も遊んだという歴史があり、江戸時代には庶民の遊びとして普及しました。
正月定番の遊び、特に女の子の遊びとして伝わってきたお手玉ですが、やったことがないという人も多いのではないでしょうか。
今回はお手玉をご紹介。
お手玉の材料や基本の遊び方、応用の遊び方についても解説します。
お手玉の材料
お手玉遊びの道具は、粒を布で包んだお手玉だけ。
誰でも簡単に遊ぶことができるからこそ、古くから伝わる定番の遊びとして広まっていきました。
まずはお手玉の中に詰められる材料についてご紹介します。
一般的な材料
お手玉の材料は、実は時代や場所によって異なります。
日本で最も一般的なお手玉の材料は小豆。
地域によって、ほかには「丸大豆」「とうもろこし」「そば」などが使われています。
場所によっては巻貝やシジミの貝殻を使用されることも。これらは通常のお手玉とまた違った独特の心地よい音を奏でることで知られています。
最古のお手玉の道具
お手玉遊び使われていた道具として、世界で最も古いものは、ヨーロッパにある黒海周辺の遊牧民の遺跡から発見されています。その素材は、羊の後ろ足の距骨。大きさは1個が親指大でした。
この羊の距骨を使ったお手玉遊びは、日本にお手玉を伝えたとされる中国をはじめ、モンゴルやオーストラリア、ヨーロッパなど世界各地で現在も行われています。
世界のお手玉の材料
では、世界のお手玉はどのような材料を使っているのでしょうか。
日本にお手玉を伝えたとされる中国では日本の大豆よりも大きい「茶の実」を使用。
ハワイにもお手玉が存在し、そこでは「フクビ」という花の実を使っています。
現在主流のお手玉の材料
お手玉の中身はさまざま。しかし天然の素材を使用していると大量生産ができないというマイナス面があります。
そのため、現在は「ペレット」というプラスチックを加工した粒を使用して、大量生産をすることが可能になりました。
また自然の素材は虫食いが発生する可能性があり、その意味でもペレットは世界で人気となっています。
【関連記事はこちら】⇩
・【お手玉】歴史(起源~由来)を解説!昔ながらの遊びを楽しもう!
・【凧揚げ】由来や起源とは?意味を知って日本文化を味わおう!
お手玉の形
お手玉の形には大きく分けて4つの種類があります。
座布団型
1つめは「座布団型」と言われているもの。
座布団のように底面が広く作られていて、安定するのが特徴です。
この形は、お手玉が全国に普及した江戸末期から明治時代にかけて普及したもの。
その名残から現在、日本で最も普及しています。
かます型
2つめは「かます型」。
穀物の入れ物である「かます」の形をしたもので、お手玉の中でもこれが最も歴史のある古い形です。
俵型
3つめは「俵型」。
日本人の主食であるお米を入れる俵に似せて作られています。
この形は江戸時代後半から流行りましたが、現在はあまり見なくなりました。
枕型
4つめは「枕型」。
こちらも同じく江戸時代後半から作られたもので、当時は主に「そばの実」や「ひえの実」が多く使われました。
【関連記事はこちら】⇩
・フットバッグの歴史・競技人口・ルール・大会【スポーツ辞典】
お手玉の遊び方(基本)
お手玉には様々な遊び方があります。まずは基本的な遊び方について紹介しましょう。
お手玉の基本動作とコツ
お手玉の基本動作は「にぎる」「上にあげる」「受ける」「手の甲に乗せる」「掴む」「渡す」の6動作があります。
これらの動作をまずは慣れることがお手玉が上達するコツです。
特に「にぎる」「上にあげる」「受ける」「渡す」は複数のお手玉を使う場合に必須スキルです。
まずはこれらの動作を練習しましょう。
両手で2個
基本の動作に慣れたら、次は両手で2つのお手玉を使って遊びます。
遊び方の順序を紹介していきます。
①両手のひらにお手玉を乗せて、右手でお手玉を投げ上げます。
②そのお手玉が空中にある間に左手に持っているお手玉を右手に渡します。
③その後、投げ上げたお手玉を左手で受けて、それを繰り返して遊びます。
片手で2個
次のステップとして、片手で2個のお手玉を扱う遊び方を紹介します。
①片手で2つのお手玉を持ちます。
②お手玉のひとつを投げ上げ、そのお手玉が空中にある状態で、もう一つのお手玉を投げ上げます。
③最初に投げたお手玉を受けて、2つ目のお手玉が空中にある間にもう一度投げ上げ、そのまま投げ上げを繰り返します。
手を前後か左右にずらしながら、空中でお手玉がぶつからないようにするのがコツです。
両手で3個
難易度が難しいとされる両手で3個のお手玉を扱う遊び方を紹介します。
①右手に2つのお手玉を持ち、左手には1つのお手玉を持ちます。
②右手にあるお手玉の1つを弧を描くように高く投げ上げ、それが空中にある間にもう1つのお手玉も投げ上げます。
③2つのお手玉が空中にある間に、左手にあるお手玉を右手に渡し、最初に投げたお手玉を左手で受けます。
④2つ目に投げたお手玉が空中にある間に、左手から渡した右手にあるお手玉を上に投げ上げます。
⑤その後、2つ目に投げ上げたお手玉を左手で受け、それを繰り返します。
お手玉の軌道が安定するように投げ上げることが上手にできるコツです。
お手玉の遊び方(応用)
基本的なお手玉ができたら、応用技にも挑戦してみてください。
片手ゆり
片手ゆりは片手だけで複数のお手玉を回す技。
難易度が一気に跳ね上がります。
カスケードジャグリング
一方向ではなく、8の字を描くように上げていく技。
最初に利き手に2個、反対の手に1個のお手玉を持ち、右上、左上と、順に逆方向に投げ上げていきます。
両手3個ゆり下がけ
お手玉の「ゆり」とは、ゆり上げる(=上に上げる)という意味。
両手3個ゆり下がけは、1個のお手玉を高く上げ、降りてくるまでに残りの2個を小さく上げる技です。
まとめ
今回は正月定番の遊びであるお手玉の遊び方について解説しました。
ご紹介した遊び方の他にもお手玉の技はたくさんあり、検定も行われています。
まずは基本の動作に慣れてから、高度な技にも挑戦してみてください。
【関連記事はこちら】⇩
・【お手玉】歴史(起源~由来)を解説!昔ながらの遊びを楽しもう!
・【羽子板】遊び方やルールを解説!飾る意味も併せてご紹介