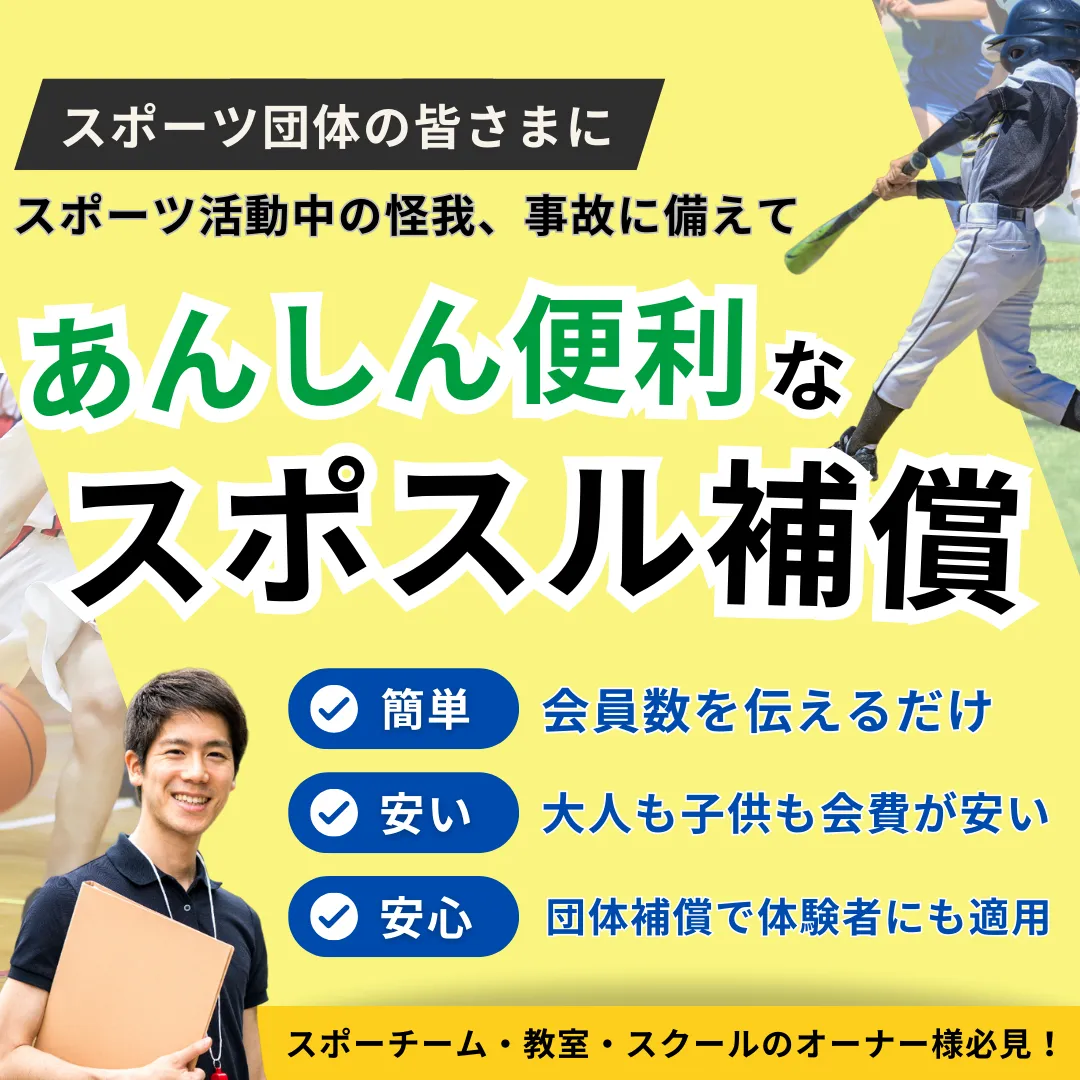野球のルールの中で正確に理解している人はとても少ないのが、振り逃げです。
振り逃げはルールブックにはどのように書かれているのかを調べると、意外な事実が。
実は振り逃げには野球のルールの本質が隠れていたのです。
今回は、振り逃げについて詳しく解説します。
【野球】振り逃げとは

振り逃げはバッターが三振になったあと1塁に向かって走り、送球よりも早く到達すればセーフになるプレーのこと。
ところが野球のルールブックである公認野球規則には、「振り逃げ」という項目はないのです。
振り逃げを成立させるルールは公認野球規則5.05「打者が走者となる場合」に書かれていますが、そこにも振り逃げという言葉は出てきません。
そして振り逃げは英語では「Uncaught third strike」または「Dropped third strike」と呼ばれています。
意味はどちらも「捕球されなかった第3ストライク」。
ここにも「振り逃げ」というニュアンスは全く入っていません。
これはどういうことでしょうか?
振り逃げが存在する理由
野球ではアウトの守備記録には「刺殺」と「補殺」の2種類があります。
刺殺は直接アウトにすること。
例えばセカンドが内野フライを捕るとアウトになりますが、このときセカンドに刺殺という記録が付きます。
一方、ショートゴロを1塁に投げてアウトにしたときはどうかというと、ショートには補殺、ファーストには刺殺が付きます。
直接アウトにしたのはファーストの選手で、ショートはアシストという意味。
このように野球のアウトには必ず「刺殺」が記録されるのです。
では、三振のときはどうなるのでしょうか。
この場合、キャッチャーに刺殺がつきます。
三振は主にピッチャーの手柄ですが、三振は投手記録で、守備記録とは別。
3回ストライクで即アウトではなく、その際にキャッチャーがボールをノーバウンドで捕球することによってアウトが成立するのです。
公認野球規則にはこれについて「捕手が第3ストライクと宣告された投球を捕らえなかった場合」に「打者は走者となる」、つまりセーフを狙って1塁に走ることができると明記されています。
キャッチャーの落球やワンバウンドの捕球はゴロの打球と同じ状態になり、1塁へ投げるかバッターランナーにタッチしてアウトにしなければなりません。
つまり振り逃げは、「アウトは刺殺でしかありえない」という野球の本質と「三振のアウトはキャッチャーの捕球で成立する」というルールから生まれるプレーなのです。
【関連記事はこちら】⇩
・【草野球】アマチュアとプロ野球の違いを徹底調査!
・【野球】タッチアップとは?条件や具体例についてご紹介!
【野球】振り逃げが発生する条件

では具体的に振り逃げが成立するのはどのような場面でしょうか。
ランナーとアウトカウント
振り逃げが成立する条件には、まずはランナーの状況とアウトカウントがあります。
1塁にランナーがいた場合、振り逃げは成立しません。
これは攻撃側が不利にならないためのルール。
1塁にランナーがいて振り逃げが成立するなら、1塁ランナーは2塁に進塁する義務ができてしまいます。
その結果、キャッチャーがわざとボールを落としてからダブルプレーを狙うことができてしまうのです。
ただし2アウトなら1塁ランナーがいても振り逃げをすることができます。
これはダブルプレーが成立しないためです。
見逃し三振やワンバウンド捕球
振り逃げはその名前から、三振のときにバットを振らなければ成立しないような印象を持たれがちですが、そのようなことはありません。
キャッチャーが捕球に失敗していれば見逃し三振でも振り逃げをすることができます。
また空振り三振でキャッチャーが捕球していても、前述のようにそれがワンバウンドのボールだったら振り逃げは成立します。
この場合、セーフになる可能性は低いと言えますが、キャッチャーの送球ミスなどがあるかもしれませんからバッターは走るようにしましょう。
振り逃げの権利が消滅するのは?
三振のときにキャッチャーが直接捕球しなかったけど、バッターもキャッチャーも振り逃げできることに気づかないということもあります。
このとき、振り逃げの権利はいつ消えるのでしょうか?
それはダートサークルを出たとき。
ダートサークルは、ホームベースを中心にした直径約8mの円で、バッターが振り逃げの権利を使うかを判断するために設置されました。
バッターが1塁に向かわずにこの円を出たときに、審判はアウトを宣言します。
【野球】振り逃げの記録方法

ルールにはない振り逃げ。
では記録上はどのように表現するのでしょうか。
まず重要なのは、ピッチャーの「奪三振」とバッターの「三振」は、振り逃げしても成立しているということ。
三振が記録から消えるということはありません。
奪三振の記録は残るのにセーフとなりますから、1イニング4奪三振という珍記録もあり得るのです。
アウトになった場合
振り逃げをしてアウトになった場合、どのようにしてアウトになったかで記録が変わってきます。
キャッチャーがタッチしたときはキャッチャーに「刺殺」。
キャッチャーが1塁に投げてアウトになったときは、ファーストに「刺殺」、キャッチャーに「補殺」がつきます。
セーフになった場合
セーフになった場合は何らかのエラーですから、その原因によって記録が変わってきます。
ピッチャーが取れないボールを投げたときは、ピッチャーの「暴投」。
取れるはずのボールをキャッチャーが逸らしたときはキャッチャーの「捕逸」。
キャッチャーの悪送球やファーストの捕球ミスなどは、ミスをした選手に「失策」がつきます。
振り逃げは自責点になる?
では振り逃げで失点した場合、ピッチャーに自責点はついてしまうのでしょうか。
振り逃げの記録は、奪三振+エラーです。
このエラーが誰の責任かによって、自責点になるかどうかが変わってきます。
つまりピッチャーの暴投なら自責点。
捕逸や失策なら自責点にはならないのです。
まとめ
ルール上に言葉が存在しない振り逃げは、「キャッチャーの捕球による刺殺で初めて三振がアウトになる」というルールから生まれたプレー。
一見奇妙なルールである振り逃げを理解することで、野球のルールの本質が見えてくるといえるかもしれません。
【関連記事はこちら】⇩
・【野球】バントの種類を目的別にご紹介!メリットやコツも調査!
・【野球】ボークとは?注意すべき13の違反行為をご紹介!