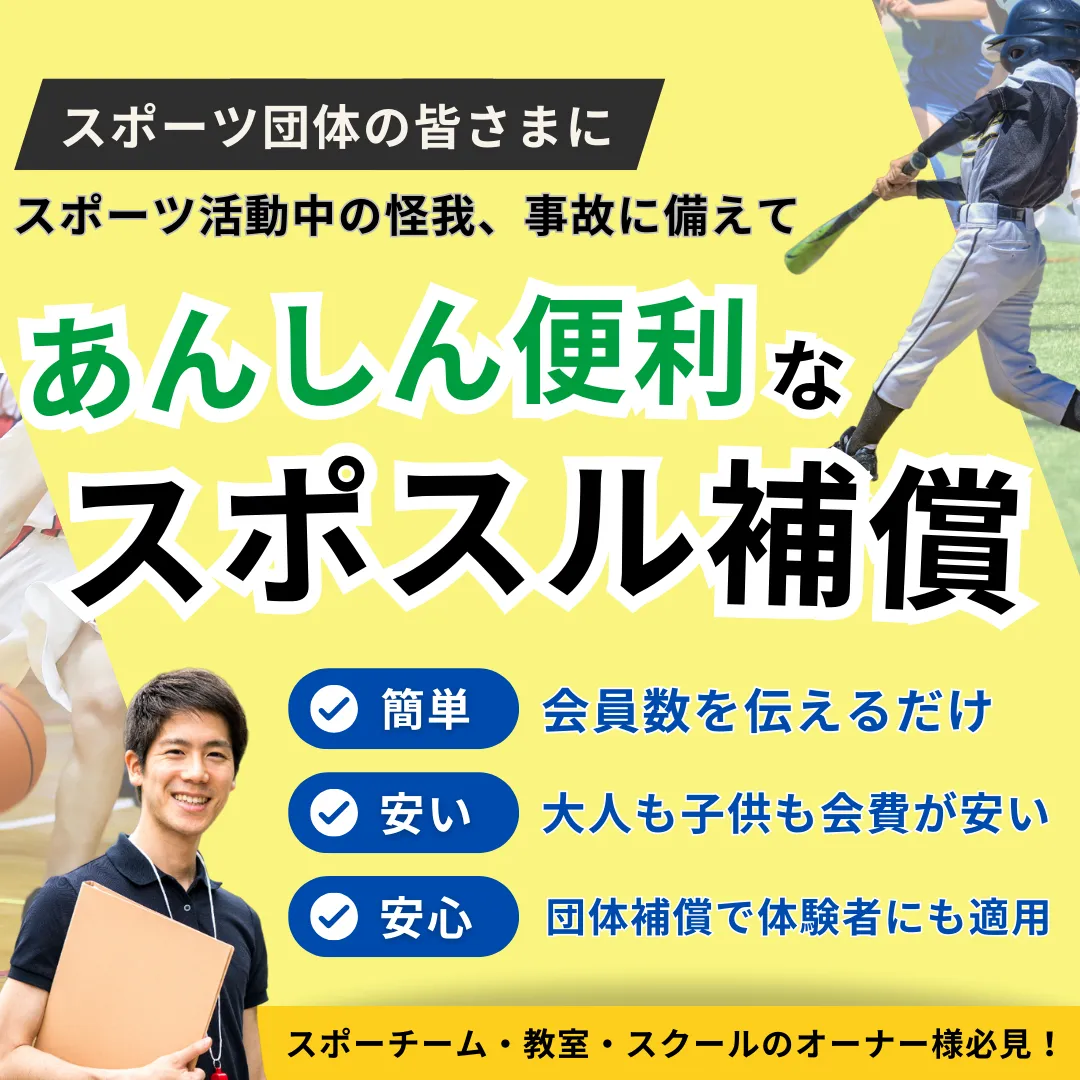世界中のスポーツの中で最も競技人口が多く、2億6千万人がプレイしているといわれているサッカー。
仲間同士で語り出すと、応援しているチームやプレイヤーについての話題は尽きませんが、必ず出てくるのが審判の判定についての意見です。
「あのジャッジは、間違いなんじゃないの?」など、判定に対する疑問や文句はいくら話しても尽きないですね。
実は筆者はサッカーの審判資格を持っているので、そんな話題の時には判定やルールの説明をすることが多いのですが、そんな時に良く質問されるのが「審判資格の取り方」です。
今回は、そんな「サッカーの審判資格の取り方」について、読者の方でもすぐに取得できる「サッカー4級審判員」からワールドカップの笛を吹く「国際審判」まで、資格の等級別に解説します。
実は、審判が胸に付けるワッペンの色で、その審判が取得している資格の種類が分かるので、併せてご紹介します。
サッカーの審判資格の種類
JFA(日本サッカー協会)の審判委員会が定めているサッカーの審判員の資格には5種類あります。
また、サッカーとは兄弟競技のフットサルの審判資格は、サッカーとは別に4種類あります。
サッカーの5種類の審判資格について、最初に取得できる「サッカー4級審判員」から順に紹介していきます。
サッカー4級審判員
サッカーの審判を目指す方が、まず最初に取得できる審判資格です。
次に紹介する3級審判員が担当できる「都道府県サッカー協会が主催する試合」より下位レベルの試合や大会の審判を務めることができます。
JFAが認定している全国の「サッカー4級審判員」の人数は、228,713名(2022年4月1日現在)で、胸に付けるワッペンの色は「緑」です。
サッカー3級審判員
「東京都リーグ」などの各都道府県のサッカー協会が主催する試合や、全国大会の都道府県予選の主審を務められる資格です。
資格保有者の人数は34,852名(2022年4月1日現在)、筆者もこの中に含まれていて、ワッペンの色は「水色」です。
サッカー2級審判員
「関東リーグ」などの全国リーグの一歩手前の、各地域サッカー協会(下記※)が主催する試合の主審を務めることができる資格です。
資格所有者は3,742名(2022年4月1日現在)で、ワッペンの色は「シルバー」です。
※地域サッカー協会:北海道、東北、関東、東海、北信越、関西、中国、四国、九州の全国9地域
サッカー女子1級審判員
最高位の「サッカー1級審判員」とは別に、体力的ハンディを考慮した女性のための資格として、JFAは「サッカー女子1級審判員」の審判資格を設けています。
「サッカー女子1級審判」員は、「WEリーグ」などの女性が参加する全国大会と、第2種(高校生)、第3種(中学生)、第4種(小学生)の試合の主審を務められます。
人数は53名(2022年4月1日現在)で、ワッペンの色は「ゴールド」です。
サッカー1級審判員
「Jリーグ」や「天皇杯」など、JFAが主催する全国レベルの試合の主審を務められる、国内最高位の審判資格です。
人数は212名(2022年4月1日現在)で、ワッペンの色は「ゴールド」です。
サッカー国際審判員
これまで紹介してきた日本国内の1級~4級の審判資格のさらに上位の資格として、ワールドカップの本大会や予選などの国際大会の主審や副審を務めるための、FIFA(国際サッカー連盟)が認定する「サッカー国際審判員」という資格が存在します。
ワッペンには、大きく「FIFA」と書かれています。
(参考)フットサル審判員(4級~1級)
フットサルの審判資格についても、参考までに解説しておきます。
フットサルの審判資格に「女子1級」はなく、サッカーと同様に4級から1級までの審判資格があり、それぞれが担当できる試合の区分やワッペンの色はサッカーの審判員の場合と同様です。
【関連記事はこちら】⇩
・サッカー審判の給料はどれくらい!?意外と高収入!?
・【サッカー】DOGSO(ドグソ)とは?適用される条件も解説!
・【VAR】ビデオ・アシスタント・レフェリーのルールや条件!
「サッカー4級審判員」の審判資格の取り方
審判資格の入り口となる「サッカー4級審判員」の審判資格の取り方は、各都道府県サッカー協会がそれぞれの方法で対応しています。
各協会が「サッカー4級新規講習会」を年に数回開催していて、「ルール解説+筆記テスト」を行って、後日合格者に資格認定の連絡をするケースが多いようです。
ただし、「一人でも多くの審判員を養成したい」という各協会側の意向があるので、筆記テストの成績に関わらず「ほぼ全員が合格」となるようです。
「審判資格を取ってみようかな」と思われた方は、各都道府県のサッカー協会のホームページ等で、講習会開催の情報を探してみてください。
また、ここで注意をしておかなければいけないことは、「将来公式戦の審判をしてみたい」とお考えの方は、「自分が審判活動をしたい都道府県のサッカー協会に申し込んでおいた方が良い」ということです。
3級審判員の資格を取ると、所属している都道府県のサッカー協会に「割り当て」の申請をして、公式戦の審判の依頼を受けることができるようになりますが、依頼される大会の会場はその都道府県内となります。
「第二審判登録」という制度で、所属している都道府県以外で公式戦の「割り当て」を受ける方法もありますが、例えば「自宅は神奈川県内だが、生活圏である東京都で審判活動をしたい」という方だったら、最初から東京都サッカー協会に所属しておいた方が、余計な手間や登録料の二重払いが発生しません。
「サッカー3級審判員」の審判資格の取り方
「サッカー3級審判員」の審判資格は、4級審判員として一定の審判活動の実績を満たした方が、各都道府県サッカー協会主催の「3級審判員認定審査会」に参加して、講義後の「筆記テスト」に合格すれば資格の認定を受けられます。
「筆記テスト」については、4級審判員の時ほどの緩さではないですが、よほどひどい点数でなければ合格できると思います。
参加資格となる実績については、「4級審判員として〇ヶ月が経過した者で、審判実績が主審と副審の合計〇試合以上で、その実績の中に主審の審判実績が〇試合以上、副審の審判実績が〇試合以上であること」など、各都道府県協会によって異なります。
また、「体力テスト」を行う都道府県協会もあるようです。
「サッカー3級審判員」の審判資格を取得すれば、各都道府県サッカー協会が主催する試合で主審を務めることができます。
「サッカー2級審判員」の審判資格の取り方
「サッカー2級審判員」の審判資格は、所属する地域サッカー協会が主催する「2級審判員認定審査会」での「筆記テスト+体力テスト+実技テスト(ピッチ上で審判の実技を審査する)」を受けて、合格した人が認定を受けます。
受験できる資格は「3級取得後2年以上で一定の経験を積んでおり、各都道府県協会の推薦を受けた人」となっているので、所属協会内からの推薦が必須となります。
また「筆記テスト」や「体力テスト」については、合格ラインが厳密に決められているので、それをクリアできない場合は不合格となってしまいます。
「サッカー2級審判員」は、全国9地域(北海道、東北、関東、東海、北信越、関西、中国、四国、九州)の地域サッカー協会が主催する試合で主審を務めることができます。
「サッカー女子1級審判員」の審判資格の取り方
「サッカー女子1級審判員」の資格は、女子の2級審判員のうちから、JFAまたは各地域サッカー協会主催の「女子1級審判員認定審査会」で試験を受けて、適格と認められた人に対してJFAが認定します。
受検資格としては「2級取得後2年以上が経っており、実績のある39歳以下の女性で、各地域サッカー協会から推薦された人」となっていて、試験内容は「筆記テスト+体力テスト+実技テスト」です。
合格すれば、WEリーグなどのJFA主催の女子の大会で主審や副審を務めることができます。
「サッカー1級審判員」の審判資格の取り方
「サッカー1級審判員」の審判資格は、「サッカー2級審判員」や「サッカー女子1級審判員」の中から、JFAまたは地域サッカー協会が主催する「1級審判員認定審査会」を受験して、合格した人に対してJFAが認定します。
受験資格は「2級取得後2年以上が経っており、実績のある34歳以下の者で、各地域のサッカー協会の推薦を受けた人」となっています。
試験内容は「筆記テスト+体力テスト+実技テスト」で、合格した「サッカー1級審判員」は、JリーグやJFLで主審や副審を務めることができます。
また、審判資格ではありませんが、「サッカー1級審判員」の中でも特に優秀な審判員の方に対して、JFAが1年の年俸制で契約するPR(プロフェッショナルレフェリー)という制度があり、2022年現在で18名(主審:14名、副審:4名)の方が活躍されています。
「サッカー国際審判員」の資格の取り方
「サッカー国際審判員」は、各国・各地域のサッカー協会や連盟がFIFAに登録を申請して、FIFAの認定を受けた方が審判資格取得者となります。
日本では(2022年現在)、男子が16名(主審:7名、副審:9名)、女子が8名(主審:4名、副審:4名)の計24名の方が認定を受けていて、世界中の国際大会で審判として活動しています。
審判資格のフィジカルテスト
3級以上のサッカーの審判資格の取得にあたっては、体力面を審査するフィジカルテストの合格も求められます。
筆者の経験上、3級の場合は合格基準を下回っても不合格にはなりませんでしたが、2級以上の場合は合格基準をクリアする必要があります。
実際にJリーグの主審を詰めていたベテランの審判員の方が、資格更新時(3級以上の審判員は、毎年「資格更新講習会」の受講が必要)の体力テストで、1級の基準をクリアすることができなかったために審判資格を失効してしまった例を聞いたことがあります。
審判員といえども、アスリート並みのフィジカル能力を要求されるテスト基準なので、ご紹介しておきます。
スピードテスト
40mのスプリント×6回(1分間隔で連続)を、下記の基準タイム内で走る。
1級審判員:6.0秒以内
女子1級審判員:6.6秒以内
2級審判員:6.9秒以内
インターバルテスト
[75mのスプリント+25mのジョギング]×各規定回数を、下記の基準タイム内で走る。
1級審判員:[75m:15秒以内+25m:18秒以内]×40本(連続)
女子1級審判員:[75m:17秒以内+25m:22秒以内]×40本(連続)
2級審判員:[75m:20秒以内+25m:25秒以内]×32本(連続)
3級審判員:[75m:25秒以内+25m:30秒以内]×24本(連続)
ワールドカップの担当審判のフィジカルテスト
筆者が3級審判員の「資格更新講習会」を受けた際に、ワールドカップの審判を務めた方の講演があり、2006年のドイツ大会の時の審判団のフィジカルテストの厳しさに驚いた経験があるので、参考までにお知らせしておきます。
ワールドカップの本大会の直前に審判団だけの事前キャンプがあり、世界中から招集された担当候補の国際審判員たちに対して行われたフィジカルテストです。
◆スピードテスト
40mのスプリント:6.4秒以内×6回(1分半間隔で連続)
◆インターバルテスト
[150mのスプリント:30秒以内+50mのジョギング:40秒以内]×20回(連続)
本大会に必要な人数よりも多めに召集された国際審判員の全員が上記のテストに参加して、「1回でも基準タイムをクリアできなかった者は、即刻母国に帰国」という厳しいフィジカルテストだったそうです。
まとめ「サッカーの審判資格を取得してみよう」
審判資格の第一歩となる「サッカー4級審判員」から、ワールドカップで笛を吹く「サッカー国際審判員」まで、サッカーの審判資格の取り方について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
ちなみに筆者が審判資格に挑戦することになったきっかけは、30代の時に友人とサッカーチームを結成し、出場の申し込みをしようとした大会に「審判資格を有する人が一人以上いる」という申込条件があったためでした。
必要に迫られて取得した審判資格だったのですが、民間のイベント会社が主催するサッカー大会の審判の依頼を受けるようになり、毎週のように審判を務めているうちに面白さとやりがいに目覚めてしまいました。
現在では「サッカー3級審判員」と「フットサル3級審判員」の審判資格を毎年更新して、週末はほぼ毎日フットサル大会の審判を務めています。
この記事を読んで審判活動に興味を持たれた方は、ぜひ「サッカー4級審判員」の資格の取得に挑戦してみてください。
【関連記事はこちら】⇩
・【サッカー】グリーンカードにはどんな意味が?実際の例も紹介!
・イエローカードはいつ消える?条件や影響について調査!