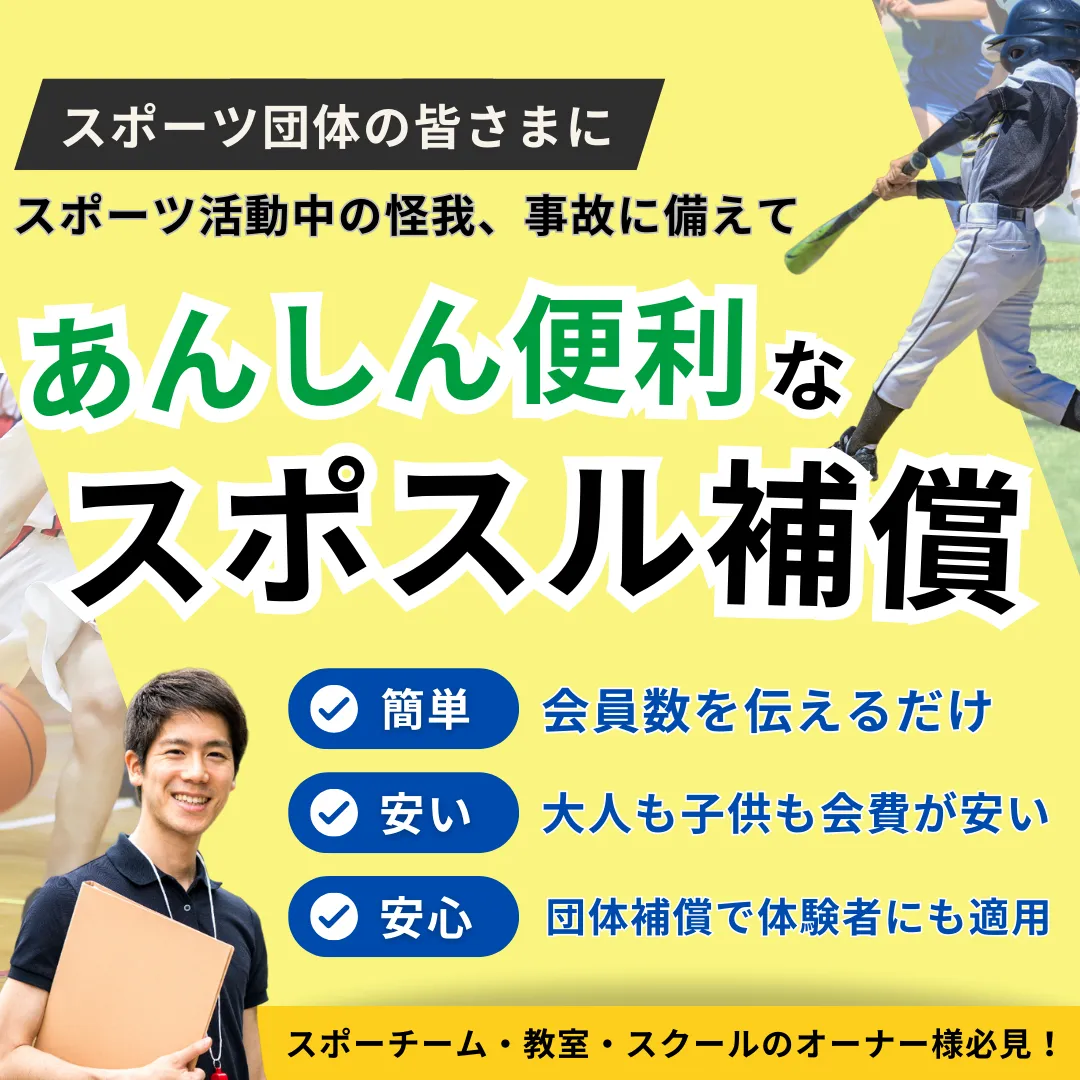野球は日本の国民的スポーツと言っても過言ではないくらいメジャーなスポーツです。
日本で行われているスポーツの中で、テレビ放送も一番多く、それだけ日本中に愛され楽しまれているスポーツです。
プロ野球選手は野球をしている人にとって憧れの存在で、将来なりたいと思う人も多いのではないでしょうか。
そのプロ野球選手が最も気をつけていることは、怪我にならない身体作りではないでしょうか。
技術の向上と同じくらい怪我の予防は大事です。
野球はコンタクトをすることが少なく、多くの場合は怪我を起こしやすい動作を繰り返すことで発生する障がいが多いです。
野球は攻撃と守備がはっきりと分かれているスポーツで、発生しやすい怪我はそれぞれ異なります。
今回は野球における「攻撃」と「守備」で起こりやすい怪我ランキングとその予防法をご紹介します。
【野球】攻撃で起こりやすい怪我ランキング
野球の攻撃ではバットを持ち、ボールを打って得点を重ねていきます。
怪我は打席に立つ時に発生する場合と、ボールを打って走っている時に起こる場合があります。
足関節靭帯損傷
攻撃時に最も多い怪我は足関節捻挫です。
ボールを打った後、ベースに向かって走り、その際セーフになるためにスライディングをします。
スライディングとは足を伸ばして滑り込むことで、セーフになりやすくなります。
野球で唯一守備選手と攻撃選手のコンタクトが発生するタイミングで、そのときに足関節を捻って靭帯損傷をしてしまいます。
もちろん思わぬコンタクトによる怪我は防ぐことは出来ませんが、ストレッチなどで足関節の柔軟性を上げることにより、多少ケガの予防をすることが出来ます。
腰痛
野球はバッティングの際に腰を回転させ、その回転力も合わさってボールを遠くに飛ばすことが出来ます。
さらに、ボールをバットにインパクトした瞬間はかなり大きな衝撃が発生します。
そういった衝撃と回旋ストレスを繰り返すことで、痛みが発生してしまいます。
日頃からストレッチを行い、腰回りの筋肉をケアすることが大切です。
ただ、身体は連動しているため、腰回りの筋肉だけでなく股関節の柔軟性も重要になってきます。
トータルしてケアを心がけることで、障がいを減らすことが出来ます。
打撲
野球はピッチャーが投げたボールを打つのですが、その投げたボールがバッターに当たる時もあります。
硬式野球のボールはとても硬く、当たれば強い痛みを伴います。
軽く当たるくらいであれば、そこまで大きな打撲になることはありませんが、打撲は放置していると内出血を起こし、その後、筋線維が硬結します。
それが原因で肉離れなど他の障がいに繋がる可能性も出てくるので、打撲した場合はすぐに応急処置・治療をしましょう。
【野球】守備で起こりやすい怪我ランキング
野球の守備では、攻撃とは違ってボールを投げるという行為が行われます。
それに加えて、バッターに打たれたボールの補球地点までダッシュして、ボールをキャッチします。
その際に、下半身に負荷がかかり怪我に繋がる可能性があります。
野球肩
野球肩という名前があるくらい野球で起こる障がいの中でも多く発生します。
これは、ボールを投げる動作によって引き起こされる肩の怪我の総称で、腱板損傷や関節唇損傷、インピンジメント症候群などのことを指します。
その中でも、野球肩の半数以上はインピンジメント症候群だと言われています。
インピンジメント症候群は、ボールを投げる際に骨と骨が繰り返し衝突することで、骨棘が形成され、痛みを発生させます。
骨棘が形成されなくても、筋肉が骨と骨の間に挟み込んで痛みを発生する場合があります。
このインピンジメント症候群を予防するには、正しいフォームを身につけることが大切です。
さらに、肩関節のインナーマッスルをトレーニングし、肩関節を安定させることで予防することが出来ます。
野球肘
野球肘も、野球肩と同様にボールを投げる動作を繰り返すことにより発生する怪我です。
ボールを投げる動作を繰り返すことで、肘に負荷がかかり、炎症や軟部線維の損傷が発生している状態のことを指します。
炎症が発生することにより、痛みや腫れが出て、肘の可動域が狭くなります。
そうすると投球フォームが悪くなり、さらに肘の負担が大きくなって悪循環が生じてしまいます。
野球肘は、小学生・中学生などの成長期で身体が出来上がっていない時期に発生しやすいと言われています。
炎症や腫れだけだと軽い治療で済みますが、悪化すれば、軟骨炎や疲労骨折などの障がいを引き起こし、手術が必要になる場合もあるので、痛みを感じた場合は投球動作を中止してすぐに病院に行くことが大切です。
野球肘を予防するためには、肘に負担のかからない正しい投球フォームを身につけることが大切です。
あとはストレッチを入念に行い、肘関節や肩関節などの関節可動域を広げることも予防に繋がります。
肉離れ
肉離れは攻撃時にも起こることはありますが、守備にも多い怪我の1つです。
守備ではボールを追いかけた時のダッシュや、キャッチからボールを投げる時の踏ん張りで発生することがあります。
肉離れを予防するには、入念にストレッチをして柔軟性を上げる必要があります。
まとめ
今回、野球における「攻撃」と「守備」で発生しやすい怪我をご紹介しましたが、繰り返すことで起きる障がいは予防することが出来ます。
予備知識を身につけ実践することで、怪我をすることなく野球を楽しみ続けることができるため、まずは今回ご紹介した怪我・障がいを理解して、予防するようにしてください。
【関連記事はこちら】⇩
・【野球】ポジションについて!番号・役割・人気順までご紹介!
・【野球グローブ】正しい型付けやメンテナスとは?プロの知識を学ぶ!