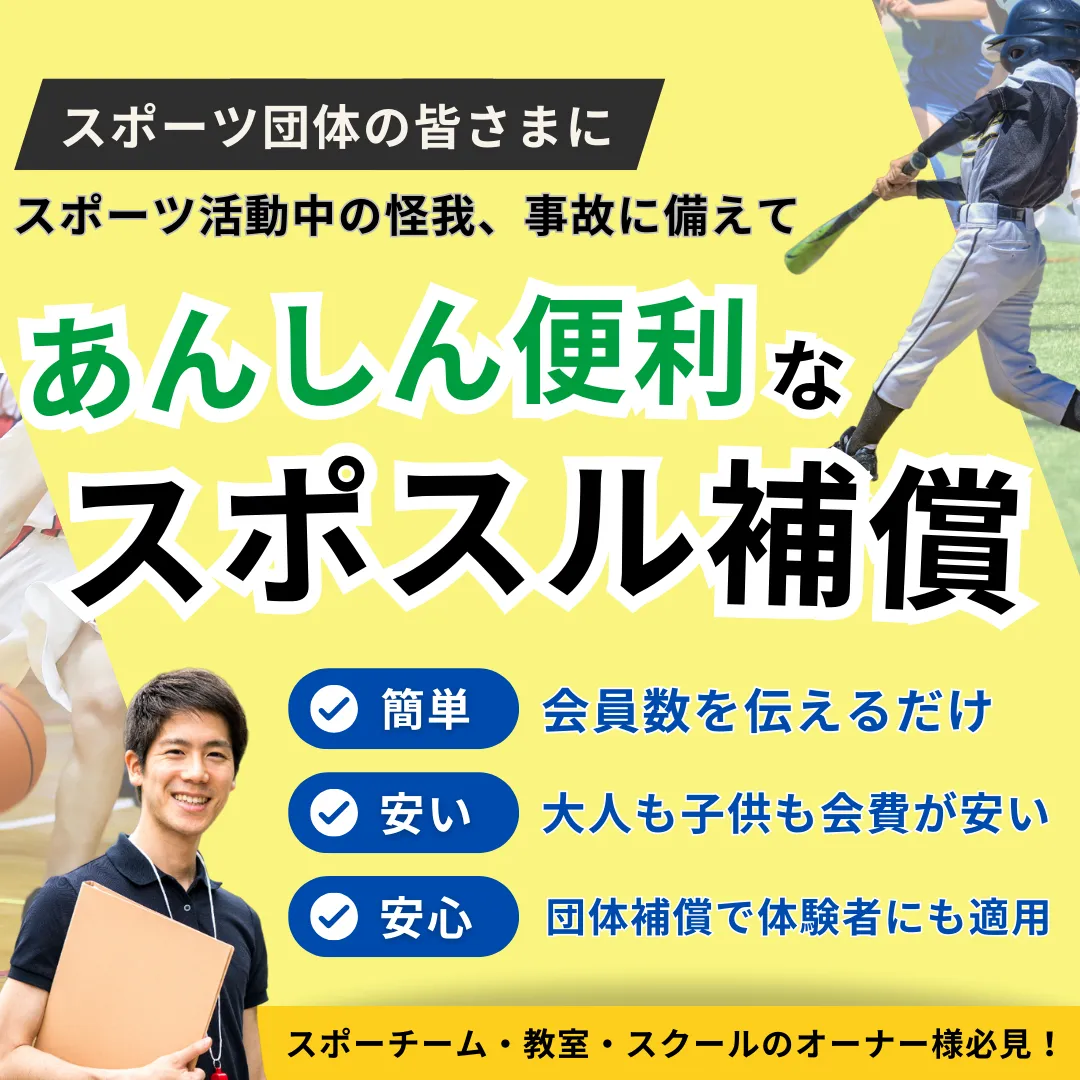低反発バットは、高校野球で2024年の春季大会から導入されたバット。いわゆる「飛ばないバット」です。
この新基準のバットはどのようなもので、なぜ導入されたのでしょうか?そして導入後の春の選抜大会では何か影響はあったのでしょうか?
今回は、高校野球の大改革のひとつである低反発バットについて特集。選手やチームの取り組み、今後の試合展開への影響についても解説します。
【高校野球】低反発バットとは?
低反発バットは、その名の通りボールの反発を低減した金属バット。素材が変わっているわけではなく、一見すると普通の金属バットです。では何が変わったのでしょうか?
低反発バットの規定
低反発バットの素材は従来の金属バットと同じ。超々ジュラルミンなどのアルミ合金がメインです。そして中身が空洞なのも同じ。
今回変わったのは次の2つの部分です。
・バットの最大直径:67ミリ未満から64ミリ未満へ
・打球部の金属の厚さ:3ミリから4ミリ以上へ
つまりバット全体が細くなり、素材が肉厚になったということ。細くなることで芯の部分が小さくなり、金属が肉厚になることで反発が弱くなるという仕組みです。
バットの重さや反発係数は?
太さや厚さが変わったということは、その他の数値はどうなのでしょうか?
まず重さは、従来の金属バットも新しい低反発バットも900g以上で同じ。細くなった分を素材が厚くなったことで相殺し、同じ重さをキープしています。
そして「低反発バット」「飛ばないバット」と言われるからには反発係数が気になるところですが、反発係数については特に規定はありません。
では実際の数値はどうかというと、低反発バットは従来のバットよりも打球速度が平均3.6%遅くなり、飛距離は5m落ちることがわかっています。
【関連記事はこちら】⇩
・【高校野球】球数制限は何球まで?経緯や規定詳細を調査!
・【高校野球】甲子園大会の雨天中止はいつ発表?日程変更についても調査
【高校野球】低反発バット導入の理由
高校野球に金属バットが解禁されたのは、ちょうど50年前の1974年3月。1973年に起こった石油ショックで木材が不足し、価格が高騰したのが背景で、木製バットよりも安く、耐久性が高い金属バットが導入されたのです。
その金属バットが、今、低反発バットへと変更されました。
低反発バット導入の時期
低反発バットが導入されたのは、2022年から。ただしこのときは完全に入れ替えるわけではなく、2年間の移行期間が設けられました。この間に選手たちにも慣れてもらうという意図。そして2024年の春の大会から選手が使えるのは低反発バットのみになりました。
ではなぜ低反発バットが導入されたのでしょうか?
そこにはいくつかの理由がありました。
野手の安全性
金属バットは反発力が高いため打球速度が速く、守備をする野手が危険であるという問題がありました。甲子園でも投手の顔面に打球が直撃して骨折したことがあり、野手の安全性を確保することが急務に。それがバットを変更する最大の要因です。
投手の負担軽減
金属バットを使う高校野球は極端な打高投低。投手は変化球を駆使し、カウントをフルに使って打たれない工夫をしなければなりません。このため投球数が多くなり、肘への負担も大きくなります。
今の高校野球では投手の負担軽減は大きな課題。低反発バットは長打の確率が減るので打たせて取る投球が増え、投球数を減らすことができるのです。
将来も通用する技術を伸ばす
高校野球からプロや大学、社会人へ進む場合、金属バットから木製バットに変わることが大きな壁になります。芯が大きくてよく飛ぶ金属バットに慣れていると、木製バットに対応できず苦労するのです。
低反発バットの直径は、実は木製バットの平均と同じ。反発力も木製バットとあまり差がないため、将来、木製バットにもスムーズに移行しやすいと考えられています。
【関連記事はこちら】⇩
・【バッティングフォーム】きれいな選手6選!経歴や特徴も紹介!
【高校野球】低反発バットの影響
飛ばないバットといわれる低反発バットですが、実際の試合でも影響はあったのでしょうか。2024年春季大会のデータから見てみましょう。
以下、過去平均はすべて2017年〜2022年の選抜大会の平均です。
打率
まずは平均打率から。
・過去平均:.251
・2024年:.233
少しですが低下しています。
長打率
低反発になったことでより重要なのは長打率。こちらは以下のようになりました。
・過去平均:.337
・2024年:.286
大きく低下しています。外野の後ろに抜ける長打が減り、単打が増えたことが分かります。
総本塁打
最も違うのがホームランの数です。
・過去平均:17.3本
・2024年:3本
2024年には大会通算でわずか3本。しかも1本はランニングホームランで、柵越えはわずか2本でした。よほどのパワーがない限りホームランは難しいことがわかります。
得点
1試合あたりの平均得点も低下しました。
・過去平均:4.3点
・2024年:3.2点
得点がなかなか取れなくなり、大量得点差も少なくなりました。
最も大きな影響は?
実際に使った選手によると、ボールが上空で失速して凡打になることが多いそう。一方、芯でとらえれば飛距離はそこまで変わらないという意見もあります。
実際に影響が大きいのは、素材が厚くなって低反発になったことよりも、むしろ最大直径が3ミリ細くなったことだそう。細くなって芯が小さくなった分、詰まったり引っかかったりして飛ばない打球が増えたことが各チームの今後の課題になっているのです。
【高校野球】低反発バットへの今後の対応
バットが3ミリ細くなるというのは選手たちにとっては大きな違い。それによって今後の高校野球にはどのような変化が起こるのでしょうか?
守備力のあるチームが勝ちやすくなる
打球が飛ばなくなると外野を抜かれる可能性は減り、外野の守備位置を決めやすくなります。一方で内野と外野の間に落ちるポテンヒットは増えることに。守備位置や外野の打球判断がより重要になります。各チームは低反発バットに対応した守備力の強化を急いでいて、今後は守備力アップに成功したチームがより勝ちやすくなるはずです。
低反発バットに早く慣れたチームが勝つ
多くの選手が戸惑っているのは、バットの細さ。いち早くそのことに気づいた選手やチームは、細いバットの芯に当てる技術の向上を目指しています。どうせ飛ばないならとあえて木製バットにする選手も。この「慣れ」にいち早く成功したチームが勝ちやすくなるはずです。
強豪チームは細いバットの芯でとらえる技術をかなり磨いてきたので、春の選抜で落ちた打率や長打率、ホームラン数は、夏の大会ではかなり向上するかもしれません。
まとめ
低反発バットに対処するためにバッターはバッティング技術をより向上させる必要があります。金属バットではスイートスポットを少し外してでもフルスイングで運ぶバッティングが主流でしたが、低反発バットではより正確なタイミングとコンパクトな腕の使い方が求められるのです。
しかしその結果、長い目で見ればバッティング技術はより向上するはず。低反発バットによって日本野球の実力がさらに底上げされることを期待したいですね。
【関連記事はこちら】⇩
・【高校野球】雨天コールドのルール一覧|これまでの経緯も詳しく解説
・【高校野球】強いのはどこ?全国の名門校・強豪校とその特徴を紹介