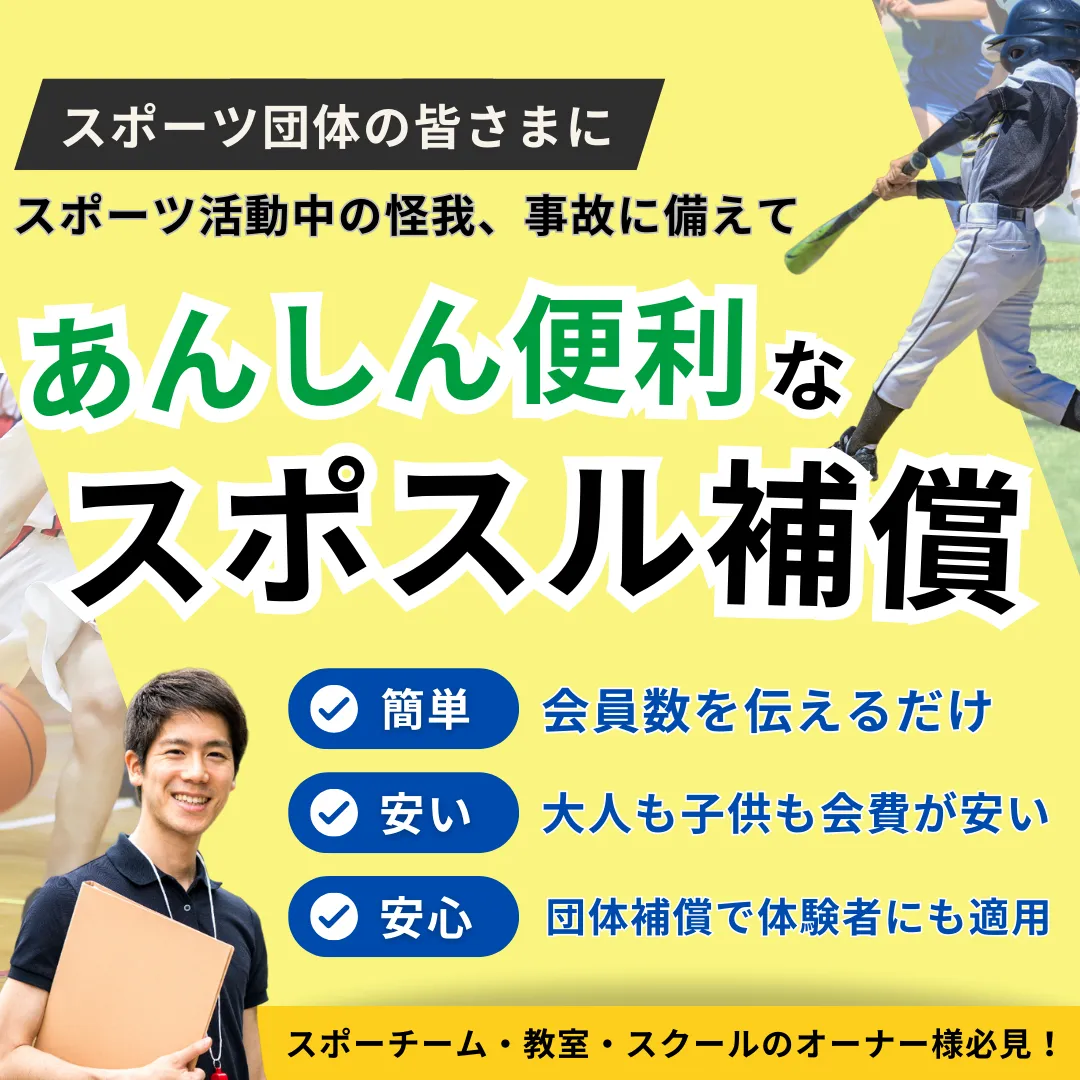半世紀以上の歴史を誇るプロ野球のドラフト会議が、今年もいよいよ10月20日に開催されます。
数々の歴史とドラマを飾ってきたドラフト会議について詳しく解説します。
ドラフト会議とは?
日本プロ野球機構(NPB)が開催するドラフト会議とは、プロ野球12球団が将来有望な選手を指名し、指名した選手の入団交渉権を獲得するために実施される新人選手獲得会議です。
現在では幅広くプロスポーツに導入されている制度ですが、日本のプロ野球では他の競技に先駆けて1965年に導入されました。
ドラフト対象選手の条件
ドラフト会議の対象となる選手の条件は次のとおりです。
・過去にNPBの球団に入団したことがないこと
・日本国籍を持っている、もしくは日本の中学校・高校・大学と、これに準ずる学校や団体のいずれかに在学した経験をもつこと
・日本の学校に在学中の場合には、ドラフト会議の翌年3月卒業見込み、大学の場合は4年間在学していること
ドラフト会議誕生の背景と経緯
今ではすっかり定着したドラフト会議ですが、この制度が導入される以前は新人選手の入団に関する明確なルールがなく、高い契約金を払う人気球団に有望選手が集中し、戦力の不均衡が大きな問題となっていました。
この状況を打開するため、1964年にプロ野球全12球団の代表者が集まり、選手の契約金高騰抑制に関して議論されたのが発端です。
この会議で、現在のドラフト会議の原案を提示したのが当時の西鉄球団代表(西亦次郎氏)で、「新人プール案」と呼ばれています。
これは、プロ入り希望選手一旦ひとつの窓口にプールし、抽選で所属球団を決めようというものでした。具体的には、NPBで新入団選手をとりまとめ、その上で各球団に選手たちを配属させる考え方です。
このアイデアに各球団は賛同し、ドラフト制度が徐々にルールを固めていきました。
【関連記事はこちら】⇩
・「育成ドラフト」とは?意味や条件・契約制度について詳しく解説!
・現役ドラフトとは?意味や仕組み・選考方法も詳しく解説!
第1回ドラフト会議開催
こうして議論された原案をベースに、約1年間を費やして細かいルールを整備し、翌1965年の11月17日に歴史的な第1回ドラフト会議が東京日比谷の日生会館で開催されました。
当日の午前10時、ドラフト会場に詰めかけた約100人に上る報道陣の異様な熱気の中で会議はスタートし、まずは両リーグの間でウェーバー方式による優先権を決めるため、この年の最下位球団であった産経と近鉄(当時)によるじゃんけん、そしてくじ引きが行われました。
その後、報道陣は会場から閉め出され、12球団が事前に提出していた指名選手リストが関係者に配布され、第一次選択が始まったのです。
まさに「歴史的なドラフト会議スタート」の瞬間でした。
ドラフト会議の仕組み
第1回ドラフト会議はなんと、じゃんけんとくじ引きだったのですね。
その後、ドラフト会議仕組みと指名方法は、くじ引き(重複選手抽選方式)や逆指名、自由獲得枠、そして育成ドラフトなど、数々の変遷と経緯をたどり、2008年から現在の仕組みへと定着しています。
現在の仕組みは次のとおりです
・1巡目選手を入札抽選
・2巡目以降は「ウェーバー方式」「逆ウェーバー方式」
・全球団が指名選択後、育成選手を選択
1巡目選手(いわゆるドラフト1位)の選手は入札抽選(くじ引き)で選択を行います。
12球団が獲得したい選手を同時に選択し、他球団と獲得したい選手が被った場合は抽選を行い、被らなかった場合は単独指名となって交渉権獲得となります。
2巡目以降は抽選を行わず、ウェーバー方式で選手選択を行います。
ウェーバー方式とは、リーグ戦の順位を元に下位のチームから順番に指名ができる方式で、順番はドラフト会議が行われる前日の順位が適用されます。
3巡目は逆ウェーバー方式となって1位のチームから順番に選択し、4巡目はまた下位のチームからと、ウェーバー方式と逆ウェーバー方式を繰り返して指名します。
ドラフト会議 過去の歴史とドラマとは
今や地上波テレビでも生中継され、指名にまつわる様々なドラマが報道されて注目を集めるドラフト会議ですが、過去には数々の歴史とドラマを生み出してきました。
人々の印象に強く残っているシーンをいくつか挙げてみましょう。
昭和の怪物・江川卓にまつわるドラマ
作新学院のスーパーエースとして高校野球を席巻した江川卓投手は、高校3年(1973年)時に阪急(当時)からのドラフト1位指名を拒否し、法政大学に進学しました。
更に卒業年(1977年)にクラウンライター(当時)の1位指名を拒否し、留年しました。
翌年(1978年)、南海、近鉄、ロッテ(いずれも当時)、阪神の4球団が1位指名し、阪神に指名されましたが、あの有名な「空白の一日」事件で巨人に入団(1978年)するという、ドラフト会議史上最大のドラマを生み出しました。
江川氏本人は一貫して巨人志望だったこともあり、ドラフトの悲喜こもごもを象徴する一連の出来事として歴史に刻まれています。
清原和博の涙
高校野球・PL学園の「KKコンビ」として空前の大活躍をした清原和博選手と桑田真澄投手。
清原選手は巨人への入団を熱望し、桑田投手は早稲田大学への進学を表明していました(1985)が、なぜか巨人が桑田投手をドラフト1位指名し、西武に指名された清原選手は涙の会見を行い、世間の注目を集めました。
最多球団指名
最多球団からの指名は、当時ノンプロ(新日鉄堺)で際立った評価を受けていた野茂英雄投手で、ドラフト史上最多の8球団から指名(1989年)され、近鉄(当時)に入団しました。
その後も、PL学園の福留孝介選手は、巨人、中日、ヤクルト、近鉄、日本ハム、ロッテ、オリックスの7球団から1位指名されましたが、拒否して一旦社会人へと進み(1995)、2年後に中日に指名され、入団しています。
最近では日本ハムの清宮幸太郎選手も7球団から指名され、話題を呼びました。
まとめ
プロ野球ドラフト会議の歴史と経緯、現在の仕組みと、過去のドラマについてみてきました。
今年も間違いなく様々なドラマが誕生し、そして素晴らしい選手たちがプロ野球への道を歩み始めることでしょう。
どんな結果となるのか、楽しみに待ちたいものです。
【関連記事はこちら】⇩
・プロ野球試合数の推移を調査!【最多154試合・最少108試合】
・【草野球】アマチュアとプロ野球の違いを徹底調査!