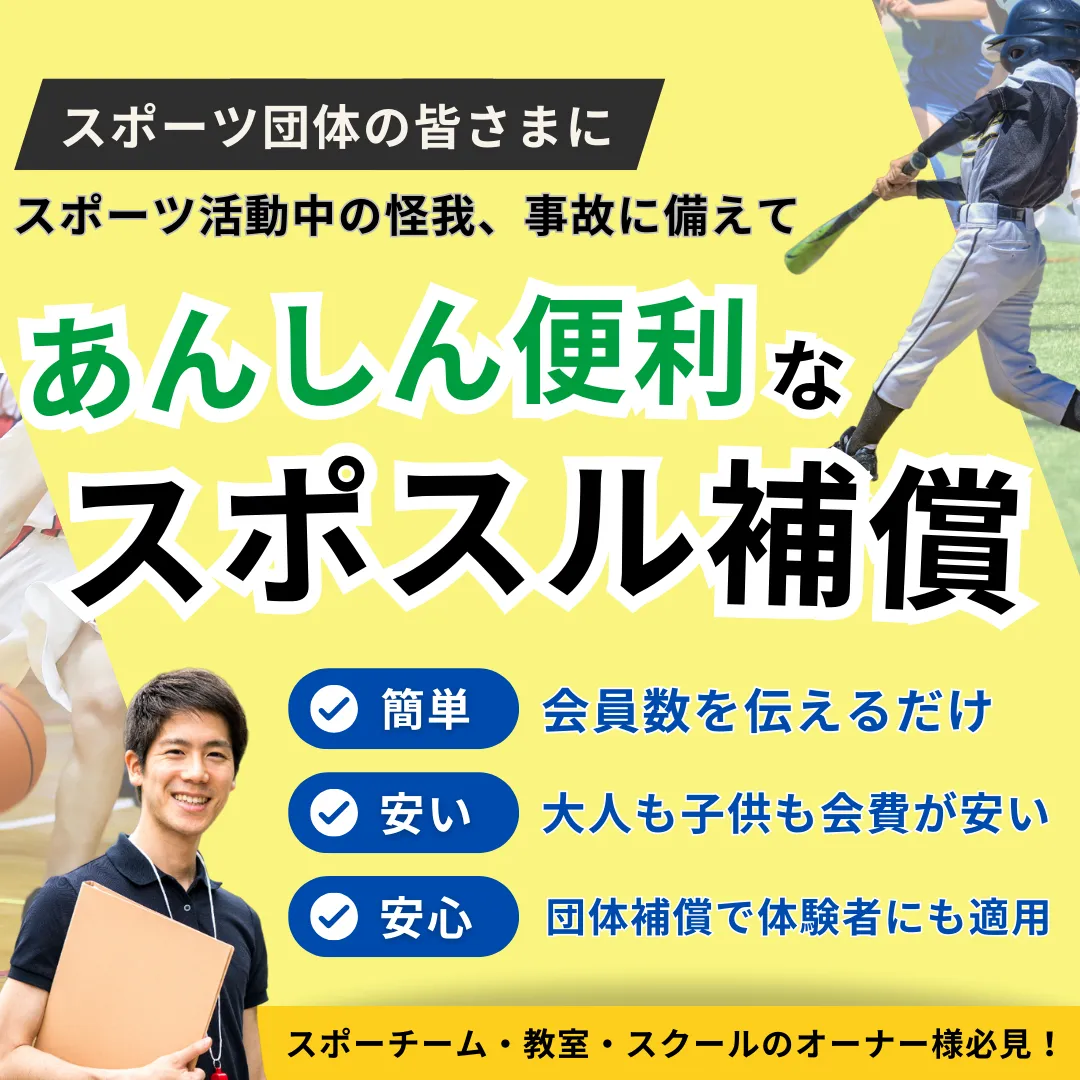マリーシアは、サッカーをしていると聞くことがある言葉。
日本では、シミュレーションに近いイメージで、あまり良くない意味で使われることがよくあります。
しかし世界では、マリーシアの意味はかなり異なるそう。いったいどういうことでしょうか?
今回は、サッカー用語の「マリーシア」をご紹介。
本来の意味や、シミュレーションとの違い、マリーシアに似た用語についても解説します。
マリーシアとは
国によって意味が異なるというマリーシア。そもそもマリーシアとはどのような意味なのでしょうか。
マリーシアの意味
マリーシア(malicia)は、ポルトガル語で「ずる賢さ」を意味する言葉。
ブラジル発祥の言葉で「機転を利かせる処世術」のことを表します。ただし実生活ではマリーシアではなくジェイチーニョ(jeitinho)という言葉を使うのが一般的です。
サッカーのマリーシアとは
サッカーのマリーシアは、ジェイチーニョの考え方を特にサッカーに当てはめて使う言葉。サッカーの試合で機転を聞かせてずる賢く立ち回ることをいいます。
マリーシアについて調べると、日本では「ずる賢いプレーのこと」という意味がよく出てきますが、この「ずる賢い」という言葉がクセモノ。ここが日本と世界でとらえ方が大きく異なるのです。
マリーシアのネガティブなイメージ
日本ではマリーシアの意味、「ずる賢い」のうち、「ずるい」が主なイメージになっています。
そのため以下のようなプレーの際に「マリーシア」という言葉を使うことが多いようです。
| ・ファールを受けて倒れ、時間稼ぎをする ・ボールをすぐに相手に渡さない ・審判には聞こえないように相手を挑発する |
このようなプレーは反則を取られなくてもフェアではないということで、恥ずかしいプレーだとされています。
マリーシアのポジティブなイメージ
しかしサッカーのマリーシアという言葉が生まれたブラジルでは、このような意味では使いません。
本来のマリーシアは、「状況に応じて機転を利かせ、試合を上手に進める賢さ」という意味。
かなりポジティブな言葉なのです。
具体的には次のようなプレーがマリーシアにあたります。
| ・ボールキープ率を上げ、ボールを回して相手を疲れさせる ・相手の陣形が整う前にすばやくフリーキックを行う ・臨機応変にポジショニングを変える ・休むべき状況で休み、走るべき場面で一気に走る |
このように試合を有利に展開するための頭の使い方、賢いプレーが「マリーシア」。決してネガティブな意味ではないのです。
ブラジルではマリーシアという言葉は使わない!
上記の例を見れば、マリーシアはサッカーの基本的な戦術であることが分かります。そのためブラジルではわざわざ「マリーシア」という言葉を使うことはほとんどありません。
日本に訪れた当時、ジーコ監督が「日本人にはマリーシアが足りない」と発言した際、「ずる賢さが足りない」という意味で広まったためにずるさが強調されましたが、実際には少し違ったニュアンスだったのです。
【関連記事はこちら】⇩
・【サッカー】宇宙開発ってなに!?気になる用語解説
マリーシアとシミュレーションの違い
ブラジルではシミュレーションとは全く違う意味で使われるマリーシア。
しかし「ずるい行為」というニュアンスがある日本では、マリーシアとシミュレーションの違いがよく分からなくなることがあります。
2つの言葉にはどのような違いがあるのでしょうか?
シミュレーションとは
サッカーのシミュレーションは、プレーの中で嘘を見せること。
具体的に見られるのは以下のようなプレーです。
| ・ボールを持った選手が、相手の足に引っ掛けられたようにわざと転ぶ ・ボールを持った選手が、相手の足に当たるように走るコースを変え、転ぶ ・相手に引っ張られたかのように転ぶ |
このようなプレーをする理由は、審判に相手の反則を取ってもらうこと。
それによってペナルティーキックなどの決定的なチャンスを得ようとします。
逆に審判はシミュレーションだと判断したら、行った選手の反則を取ります。
【関連記事はこちら】⇩
・【一覧】サッカーの反則行為を徹底紹介!色々な種類がある!?
マリーシアとシミュレーション
ネガティブな意味のマリーシアは、シミュレーションを含むずるいプレーだと思われがち。
しかし実際にはマリーシアとシミュレーションは大きく異なります。
最大の違いはフェアプレー精神の有無です。
| ・マリーシア:フェアプレー精神があり、ルールに則った賢いプレー ・シミュレーション:フェアプレー精神はなく、審判を欺こうとするプレー |
実はブラジルにはタックルやチャージを受けて転んだと思わせるシミュレーションがとても上手い選手が多く、このこともマリーシアとシミュレーションの混同の原因となっています。
【関連記事はこちら】⇩
・【サッカー】シミュレーションとは?反則行為についてもご紹介!
マリーシアと似た意味の言葉
発祥の国のブラジルではあまり使われていない「マリーシア」。ではブラジルでは、どのような言葉で表現しているのでしょうか。
マランドラージェン
マリーシアはブラジルでサッカーをするなら基本的に身についているもの。
ではその中でも、特に相手の隙につけこんだり、うまく時間を稼いだりすることがうまい選手をどう表現するのでしょうか。
そういった選手に使うのは、「マランドラージェン」という言葉です。
マリーシアと同じようにポジティブな意味ですが、より「狡猾さ」「したたかさ」を強調した言葉。ジーコ監督が日本選手に足りないと言ったものにより近いニュアンスになります。
【関連記事はこちら】⇩
・【サッカー】日本代表歴代監督一覧|各監督の特徴と実績もご紹介!
・【ブラジル】サッカーはなぜ強い?特徴や理由なども詳しく解説!
カチンバ
実は日本でイメージされるようなネガティブな意味の「ずるさ」を表す言葉もあります。
それは相手を陥れるずるさという意味の「カチンバ」です。
ポルトガル語のサッカー辞書によると「カチンバ」の意味は「相手選手をいらつかせるための、試合中におけるさまざまなマランドラージェン」。
つまり相手を挑発して冷静なプレーができないようにしたり、退場に追い込んだりするようなプレーがカチンバです。
ちなみにカチンバを得意としている選手は「カチンベイロ」。
南米に多いカチンベイロの挑発行為に乗って敗戦すると「カチンバにハマった」と報道されます。
まとめ
日本では「ずるさ」が強調されがちなマリーシア。本来は「賢いプレー」というニュアンスが強い言葉です。
フェアプレーの範囲で自分に有利となるようプレーをするのはサッカーの基本。サッカー選手ならぜひ身につけたい技術といえます。
シミュレーションは論外。カチンバはあまり褒められたものではありませんが、マランドラージェンはぜひ目指したいものです。
【関連記事はこちら】⇩
・【サッカー】レッドカードの条件とは?出場停止期限や処分も解説!
・【サッカー】ファール一覧|基準や種類などを詳しく解説!