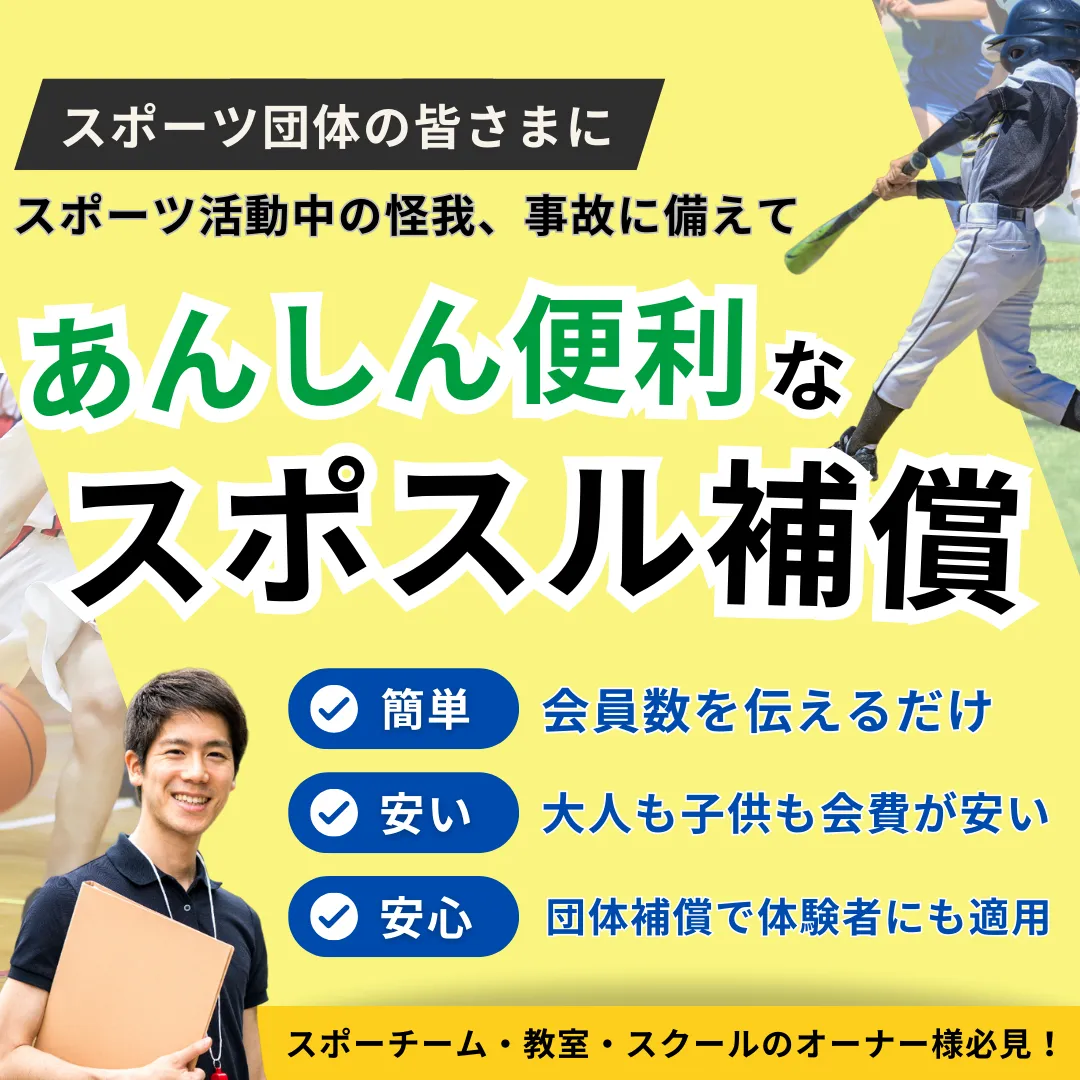横綱は大相撲の力士の頂点。
この横綱になるのがとても大変であることは、多くの人が知っているはずです。
ではそもそも力士とはどういった人たちで、横綱まで上り詰めるためにはどのような条件をクリアする必要があるのでしょうか。
今回は、横綱になるまでの道のりを調査。
力士のトップである横綱として認められるための条件もご紹介します。
【相撲】力士とは
まずは力士とは何かについて解説しましょう。
力士と呼べるのは?
力士はいわゆる相撲をする人全般を言うこともありますが、厳密には相撲部屋に所属して四股名を持ち、プロとして大相撲に参加している選手のことになります。
つまりプロではない高校相撲の選手や、大学相撲などのアマチュアで活躍する選手は力士とは呼ばれないのです。
またプロであっても幕下以下の選手の場合は、力士養成員と呼ばれることもあります。
力士の歴史
もともとは農作物の実りなどを祈り、神様に感謝を捧げるための神事としての側面が強かった相撲。
古事記などにおいては、かのタケミカヅチとタケミナカタなどの神々が、国譲りを巡って相撲を取ったという記述も残されているほどです。
化粧まわしが、神社の注連縄(しめなわ)に似ていると思ったことのある人も多いのではないでしょうか。
それらはつまり、神様の依り代(よりしろ)になって神通力を備え、そのご利益を受け取る特別な存在として扱われていたという証でもあるのです。
【関連記事はこちら】⇩
・【相撲】歴史(起源~現在)を調査!誰がいつ始めたの?
【相撲】力士になるには
横綱になるためには、まず第一に力士として認められなければなりません。
この段階から厳しい試練が始まっています。
新弟子検査
力士になるためには、まず新弟子検査に合格して、部屋入りを果たすことから必要です。
日本大相撲協会によれば、新弟子検査の基準は以下のようになっています。
義務教育を修了した健康な男子であり、所定の身長・体重の基準を満たした上で、一般的には23歳未満。
指定の社会人や大学のアマチュア大会で、一定の成績を残した人については25歳未満であること
この所定の身長と体重というのは、身長167cm以上、体重67kg以上を指します。
例外として、三月場所の新弟子検査受験者の中で、中学卒業見込み者に限り少しハードルが下がり、身長165cm以上、体重65kg以上です。
身長と体重が一定以上なければ、力士になることさえできない理由は、大相撲が無差別級だから。
一定以上の身長と体重がなければ危険が避けられないためなのです。
【関連記事はこちら】⇩
・【相撲】子どもに習わせるメリットをご紹介!将来に繋がるスポーツ!
【相撲】関取になるには
力士と関取。二つの名前は混同されがちですが、実は全く意味が異なります。
関取とは
関取というのは本来は大関のことを指す異称だったそうです。
それは名乗っただけで関所を通ることができる、ということに由来。
現在は十両以上の力士のみを関取と呼ぶのが一般的となっています。
関取の待遇
十両以上の関取と、幕下以下の力士たちとでは待遇が大きく異なります。
大きな違いは、関取になると日本相撲協会からきちんと月給が出るということ。
場所ごとに与えられることになる力士褒賞金、引退時の退職金も関取とそれ以下では大きく異なります。
化粧まわしが用意され、本場所で毎日土俵入りを行うのも関取のみ。
他にも多くの待遇の差があります。
また結婚を許され、ファンにサインを書くことが許されるのも実は関取のみです。
関取への道のり
では、その関取になるためにはどのようにすればよいのでしょうか。
一般的に多くの力士は一番下の序ノ口からスタートし、本場所で勝ち越すことで階級を上がっていきます。
力士は基本的に勝ち越せば番付が上がり、負け越せば番付が下がる仕組み。
力士の番付は、毎場所後に行われる番付編成会議で上下することになります。
番付は下から順に、序の口、序二段、三段目、幕下。ここまでは力士養成員です。
そしていよいよ十両になり、関取と呼ばれます。
【関連記事はこちら】⇩
・【相撲】階級一覧|格付けや待遇なども詳しく解説!
・【大相撲】懸賞金の制度や獲得ランキングについて徹底調査!
【相撲】横綱になるには
関取になっても、その先には長い道のりがあります。
横綱までの道のり
番付が十両となり関取と呼ばれるようになっても、その上には前頭、小結、関脇、大関といくつもの番付があります。
ここでも勝ち越せば番付が上がり、負け越せば下がる仕組み。
周囲の力士の実力が格段に上がる中、勝ち越しを重ねて番付を上げていくことになります。
そして大関の地位で一定の条件をクリアすることで、ようやく横綱になれるのです。
その名称は、横綱だけが腰に締めることを許されている白麻製(しろあさせい)の綱に由来しています。
横綱になるための条件
その横綱に認められるためには、どのような条件をクリアする必要があるのでしょうか。
大相撲の横綱審議委員会が定める横綱推薦の内規によれば、品格、力量が抜群であることが大前提とされています。
また実際的な条件としては、原則として以下をクリアする必要があります。
・大関で二場所連続優勝、またはそれに準ずる成績を上げること
・出席委員の3分の2以上の決議を得ること
・品格に関して日本相撲協会で十分に審議すること
しかし現在は、二場所連続優勝に「準ずる」の部分が、より厳格になっています。
以前の条件
実は昭和の時代は「優勝に準ずる成績」の部分がかなり甘い解釈になっていました。
そのため、優勝をせずに横綱になった力士が大勢いたのです。
昭和に横綱に昇進した力士のうち、二場所連続優勝で横綱になったのは4人のみ。この基準を満たしていない力士が何人も横綱に昇進していました。
そして優勝経験のまったくない双羽黒が横綱になり、その後一度も優勝することなく廃業。
これが問題となり、その後は昇進基準が厳格化されました。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
長い長い道のりを経て、その腰に横綱を巻く関取は、やはり風格も重みも段違いであるようです。
大相撲中継を見る時、そして横綱の取り組みを見る時はぜひ、その地位の重みと歴史に思いを馳せてみるのもいいかもしれません。
【関連記事はこちら】⇩
・相撲の親方になるには!?どんな人がなれるのかを解説!
・相撲力士のお給料とは!?収入事情について徹底解説!!